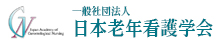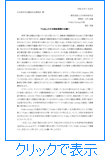トップページ > 関連団体情報 > 各種ご案内
- 「第32回国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI2017)」京都開催会議参加のご案内
《早期登録期限のお知らせ》- 公益社団法人 認知症の人と家族の会
- 【日程・会場】
- 2017年4月26日(水)~29日(土) 国立京都国際会館
- 【公式サイト】
- http://www.adi2017.org/
- 【趣旨】
- いよいよ4月26日からの「ADI2017」まで、100日を割るところまで来ました。
- すでに国際会議全体のプログラム作成も大詰めに入っており、全体会の演者の紹介などが公式ホームページに順次掲載されています。(26日参加受付開始。27~29日開会式、全体会、分科会等)
- この国際会議に参加いただくためには、公式ホームページの登録ページからの事前登録が必要です。登録時期によって登録料が異なりますので、早めの登録をお勧めいたします。
- ① 早期登録 2月6日(月) まで
- ② 前期登録 4月7日(金) まで
- ※4月8日以降は、会場での当日受付となります。
- インターネット登録のみとなっておりますので、公益社団法人 認知症の人と家族の会の参加登録方法マニュアルも参考にしてください。また、登録区分や登録方法などで不明の点がある方は、「家族の会」事務局までお問い合わせ願います。 現在、全体会に加えて、発表公募の査読通過者による分科会(約150人)やポスター発表(約400件)、当事者等によるワークショップ(5枠)などの編成(会議プログラム日程)が進められています。
- また、ADI加盟85ヵ国・地域の展示ブース、研究機関・大学・企業の発表ブース、「家族の会」企画のおもてなしカフェなどの企画も準備されつつあります。
- さらに、26日のADI総会(17:30~)の前に、世界保健機関とイギリスアルツハイマー協会との共催によるプレ・シンポジウム(Building a Dementia-Friendly World)の開催が決定され、世界の認知症にやさしい地域づくりの先進事例のプレゼンやパネルディスカッションが予定されています。
- みなさまの参加を歓迎いたしますとともに、所属されている団体や職場の方々にも、ぜひお知らせをいただきますようお願いいたします。
- 第6回 杉浦地域医療振興助成の募集のお知らせ
- 公益財団法人杉浦記念財団
- 【趣旨】
- 我が国では、人類未曾有の超高齢社会を迎えて、「地域包括ケア」の実現とともに「健康寿命 の延伸」が課題となっています。 そこで、本財団では、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び介護福祉従事者等の多職種が 連携して、「地域包括ケア」「健康寿命の延伸」を実現しようとする研究を助成します。
- 【募集期間】
- 2017年 1月 1日(日)~ 2017年 2月 28日(火)
- 【応募資格】
- 日本国内で研究する個人又は団体、とりわけ、高齢者人口が急激に増加している都市で 地域医療従事者等として実際に業務を行っている多職種の皆様の応募を期待しています。
- 同一研究内容に関する申請は、1 件に限ります。
- 既に本助成を受けた同一個人又は団体が、2 年連続で同一内容の助成を申請することはできません。
- 他団体(科学研究費等)から同一内容で助成を受けている、又は助成を申請中の場合は、応募書類に必ず記載してください。
- 【助成金額】
- 研究は、総額 1500 万円で、1 件につき 300 万円を限度とします。
- ※活動については、募集要項、応募申請書が異なります。
- 【詳細情報】
- 選考対象などの詳細情報・応募方法はなどは下記画面よりご確認ください(外部サイト).
- http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html
- 平成28年度 長寿科学関連国際学会派遣事業 第3期募集のお知らせ
- 公益財団法人長寿科学振興財団
- 【趣旨】
- 本事業は、海外で開催される長寿科学関連国際学会に日本国内において長寿科学に関する研究で優れた研究成果をあげた若手研究者又は有望な研究を行った若手研究者を研究発表のために派遣し、長寿科学研究の国際協力・国際交流に資することを目的とし、かつ我が国の研究の中核となる人材育成に寄与する。
- 【第3期募集期間】
- 平成28年9月1日(木)~ 平成28年10月28日(金)
- 【国際学会開催期間】
- 平成28年12月1日(木)~ 平成29年3月31日(金)
- 【詳細情報】
- 詳細情報・応募方法はなどは下記画面よりご確認ください(外部サイト).
- http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000003800/hpg000003704.htm
- 平成28年度長寿科学研究者支援事業募集のお知らせ
- 公益財団法人長寿科学振興財団
- 長寿科学研究に携わる研究者の研究活動を幅広く支援することにより、研究者の育成と長寿科学の振興を図るために、研究課題の募集を行います。
- 応募された研究課題は、長寿科学研究者支援審査評価委員会において総合的評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき研究費が交付されます。
- 【助成対象課題】
- 募集研究課題は予防・診断・治療法の開発分野、看護・介護分野など長寿科学に貢献できるすべての分野を研究課題とします。
- 【提出期間】
- 平成28年3月14日(月) ~ 4月11日(月)必着
- 【詳細情報】
- 詳細情報・応募方法はなどは下記画面よりご確認ください(外部サイト).
- http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000003900/hpg000003801.htm
- 長寿科学振興財団より「若手研究者表彰事業」のお知らせ
- 長寿科学研究に携わった若手研究者の研究活動を幅広く支援することにより若手研究者の育成と長寿科学の進行を図ることを目的に、優れた研究成果を上げた若手研究者を「長寿科学賞」として表彰を行っております。
- 今年度につきましては、下記の期間に表彰の候補者の推薦を受付けいたします。なお、候補者の推薦については原則として当該候補者の属する機関の部門の長、又は所属機関の長の推薦によるものといたします。つきましては、貴学会員の皆様にエントリ―頂きたく、本事業の周知のご協力をお願い申し上げます。
- 事業名:
- 若手研究者表彰事業
- 推薦書類の受付期間:
- 平成27年6月1日(月)~平成27年6月30日(火)
- 推薦方法:
- 財団HPより推薦書類一式をダウンロードし、項目記入のうえ、書留郵便または宅配便により財団まで送付
- 財団HP:
- 「若手研究者表彰事業」
- http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000000200/hpg000000137.htm
- 送付先:
- 公益財団法人長寿科学振興財団 事業推進課
- 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1-1
- あいち健康の森健康科学総合センター4階
- Tel: 0562-84-5411 Fax: 0562-84-5414 E-mail: research@tyojyu.or.jp
- 平成27年度長寿科学研究者支援事業募集のお知らせ
- 公益財団法人長寿科学振興財団
- 長寿科学研究に携わる研究者の研究活動を幅広く支援することにより、研究者の育成と長寿科学の振興を図るために、研究課題の募集を行います。
- 応募された研究課題は、長寿科学研究者支援審査評価委員会において総合的評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき研究費が交付されます。
- 【助成対象課題】
- 募集研究課題は予防・診断治療法の開発分野、看護・介護分野など長寿科学に貢献できるすべての分野を研究課題とします。
- 【提出期間】
- 平成27年3月16日(月) ~ 4月10日(金)必着
- 【詳細情報】
- 詳細情報・応募方法はなどは下記画面よりご確認ください(外部サイト).
- http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000003900/hpg000003801.htm
- フィリピン台風30号・看護活動支援募金のお願い
- この度フィリピン第30号の被害に対し,看護活動支援募金活動を開始することとなりました.
 philippines donation-->
philippines donation-->
- 「日本骨粗鬆症学会」第4回骨粗鬆症マネージャーレクチャーコース開催のご案内
- 一般社団法人日本骨粗鬆症学会では骨粗鬆症治療におけるリエゾンサービスの普及を目的に,骨粗鬆症の診療支援サービスに関わっていただく医療職の方を対象にした教育プログラムを策定し,普及・推進をすすめています.レクチャーコースの内容は骨粗鬆症の総論から診断・治療にわたる,基本的な内容を中心としています.
- 日 時 : 2014年3月9日(日) 12:00~16:00
- 会 場 : 明治大学駿河台キャンパス
- ※詳細は,日本骨粗鬆症学会のホームページをご覧ください.
- 日本老年医学会Frailty Workingによる「Frailty」の日本語訳募集
- この募集は2013年8月31日に締め切りました。
日本老年医学会では、これまで「虚弱」と訳されてきた「Frailty」が、- ①ネガティブな印象を与える
- ②「Frailty」の多面的な要素や身体・心理・社会的特性を表現できてない
- 等の理由により、このたび日本語訳を検討するワーキングを立ち上げ、日本老年学会構成学会にも日本語訳募集の案内がありました。
- つきましては下記の要領にて、本学会員の皆まさからもご意見をお寄せください。
- 依頼文書の詳細は次のとおりです。
- 【「Frailty」の日本語訳募集のお願い】
世界で最も高齢化が進んでいるわが国において、高齢者が機能障害(Disability)や要介護状態に至ることを予防するため、高齢者の健康状態及び日常生活機能(ADL)をよりよく理解することが求められています。老年医学の分野においては、現在Frailtyが非常に注目されています。Frailtyは高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、機能障害、要介護状態、死亡などの不幸な転機に陥りやすい状態とされます。Frailtyは生理的な加齢変化と機能障害、要介護状態の間にある状態として理解されていますが、その定義、診断基準については世界的に多くの研究者たちによって議論が行われているにもかかわらず、コンセンサスが得られていない状況です。現在最もよく使われているのはFriedらによる体重減少、易疲労感、握力低下、歩行スピード低下、低活動の5つのうち3つ以上満たせば、Frailであるという基準です。しかしながら、現在多くの研究者はこのような身体的側面だけでなく、認知機能低下など精神・心理的要因や社会的な要因を含めるべきであると考えています。 Frailtyの日本語訳について現在「虚弱」が使われていますが、いずれの文字もNegativeな印象を持ち、Frailtyの持つ多面的な要素、及び身体的、精神・心理的、社会的特性を十分に表現できているとは言いがたいと思われます。また、Frailtyにはreversibilityといった側面も含まれ、Frailな高齢者を早期に診断し、適切な介入をすることにより機能障害に陥らず、生活機能が維持できることが期待されます。 すでに、ロコモ、サルコペニアは用語として定着しているように思われますが、Frailtyに関しては「虚弱」と訳される一方で、介護保険制度において二次予防事業対象者、要支援高齢者という用語が使われ、これらはいずれもFrailな高齢者として認識されているため、混乱を招いています。このような現状に鑑みて高齢化が最も進んでいる日本からFrailtyに対する概念を構築し,世界に発信する必要があると考え、日本老年医学会では数名のメンバーから成るFrailty workingを結成して諸課題に取り組むことになりました。 Frailty workingでは最初の作業としてFrailtyに対応する新しい日本語を作ることで、わが国に新しいFrailtyの概念を定着させるのが第一歩ではないかと考えました。そこで、今回日本老年医学会が中心となり、広く日本老年学会に所属する会員の方々にFrailtyに対応する日本語訳を公募することといたしました。 つきましては、大変ご多忙とは存じますが、平成25年8月末日までに日本老年医学会事務局(jgs@blue.ocn.ne.jp)まで、日本語訳の案をお送りいただければ幸いです。Frailty workingにて審議の上、決定したいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会