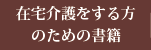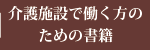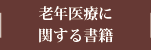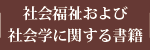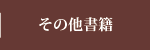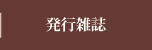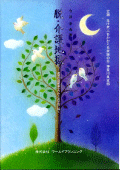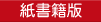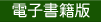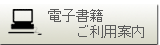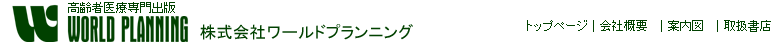
脱・介護地獄 -痴呆性高齢者をかかえる家族に捧ぐ-
著者:今井幸充 企画:呆け老人をかかえる家族の会・神奈川県支部
体 裁
A5判・210頁
刊行日
1999年4月
ISBN
9784948742338
内容紹介
「親族の無責任な干渉」「無意味な同情」
「理想と現実のギャップ」
・・・数え上げればキリがないほど,痴呆性高齢者をかかえる家族はさまざまなものと闘っています.
本書は,介護家族の心身の負担を軽くし,気張らず自然にまかせた介護をするための応援書です.
目次
- はじめに
- 第一章 老化とボケ
- 一 こころの老化
- 二 三つのボケ
- 第二章 痴呆が起こったら
- 一 歳を取ると、もの忘れは当たり前
- 二 こんなことがみられたら要注意
- 三 痴呆と気づいたとき
- 四 医師にできること…できないこと…
- 五 担当医師との上手なお付き合い
- 六 病院と施設の違い
- 二 こんなことがみられたら要注意
- 第三章 痴呆と家族
- 一 崩れ落ちたサザエさん一家
- 二 家族は「隠れた患者」
- 三 介護は負担を伴う
- 四 介護を少し楽するために
- 五 在宅介護は当然なのか
- 六 「恩」「孝」「忠」の家族観
- 七 世間体と同居
- 八 長男がみるとだれが決めた
- 九 自分の老後は自分で決める
- 一〇 介護者の条件
- 一一 介護者の介護者
- 一二 ボケたから優しくしろとは虫がいい
- 一三 介護にも向き不向きがある
- 一四 TVの人生相談って…
- 一五 他人は無責任
- 一六 介護者の周りの皆さまへ
- 二 家族は「隠れた患者」
- 第四章 楽して介護する方法
- 一 痴呆性高齢者も戦っている
- 二 感情は忘れない
- 三 介護を楽にする最大のヒント
- 四 できることはたくさんある
- 五 できないことは、できない
- 六 家事はいっしょに
- 七 がんばるだけが能じゃない
- 八 介護者は司令塔
- 九 遠くの親戚よりも近くの他人
- 一〇 介護者の生活を第一に
- 一一 呼び寄せ老人の幸不幸
- 一二 介護者が留守のとき
- 一三 さぼることも大切
- 一四 家事の手を抜いて
- 一五 気張らず介護を
- 一六 介護も生活の一部
- 一七 寝たきりのほうが介護は楽
- 一八 優しくなれとはいうけれど
- 一九 介護の限界は自分で決める
- 二〇 入所施設をあらかじめ決めておく
- 二一 施設介護も一つの選択
- 二二 施設の選び方
- 二三 施設に求めるもの
- 二 感情は忘れない
- 第五章 ちょっと視点を変えた介護方法
- 一 まずは一服
- 二 介護者のイライラが移る
- 三 何度聞けば気がすむの
- 四 もの忘れは治らない
- 五 財布が盗まれる
- 六 悪口を言いふらす
- 七 性への異常な関心
- 八 あなたの親なのに…
- 九 あなたは夫じゃない
- 一〇 徘徊には理由がある
- 一一 徘徊事故を防ぐ方法
- 一二 女性に多い夕暮れの騒ぎ
- 一三 できることには手を貸さない
- 一四 できないことをさせるのは大変
- 一五 「駄目」とはいってはみたが
- 一六 いうことを聞いてくれない
- 一七 思うようにならないのが介護
- 一八 お風呂なんて嫌
- 一九 失禁は介護の分かれ目
- 二〇 オムツ交換はさりげなく
- 二一 洋式トイレに棲む魔物
- 二二 ポケットのなかのうんち
- 二三 他人の介護法が役に立つとは限らない
- 二 介護者のイライラが移る
- 参考・一 長寿の国、日本
- 一 高齢社会の到来
- 二 高齢少子化時代
- 三 要介護高齢者
- 四 急騰する高齢者医療費
- 五 新ゴールドプラン
- 六 公的介護保険制度
- 七 介護保険給付対象者とその内容
- 八 財源確保は大丈夫か
- 二 高齢少子化時代
- 参考・二 痴呆のメカニズム
- 一 痴呆は何人いるのか
- 二 アルツハイマー型痴呆は増えているのか
- 三 脳血管性痴呆の減少
- 四 ボケの起こり
- 五 アルツハイマー病
- 六 アルツハイマー病とアルツハイマー型老年痴呆
- 七 アルツハイマー型痴呆の病態
- 八 痴呆の中心症状
- 九 記憶の障害
- 一〇 見当識の障害
- 一一 言葉の理解の障害
- 一二 判断力の障害
- 一三 性格の変化
- 一四 その他のボケの症状
- 一五 痴呆と紛らわしい高齢者のうつ病
- 二 アルツハイマー型痴呆は増えているのか
- 参考・三 痴呆はどのように進行するのか
- 一 痴呆の程度
- 二 アルツハイマー型痴呆の経過
- 三 脳血管性痴呆の経過
- 四 異常行動の出現
- 五 痴呆性高齢者の余命
- 六 痴呆性高齢者の死因
- 七 薬の話
- 二 アルツハイマー型痴呆の経過
- 稿を終えて
関連書籍
 認知症のADLとBPSD評価測度
認知症のADLとBPSD評価測度
お問い合わせ | 特定商取引に関する法律に基づく表示 Copyright (C) 2009 WORLD PLANNING Co, Ltd. All Rights Reserved.