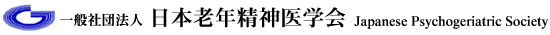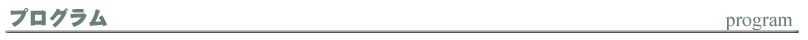- 丂僩僢僾儁乕僕丂亜丂妛弍廤夛丂亜丂戞26夞擔杮榁擭惛恄堛妛夛丂亜丂僾儘僌儔儉

-
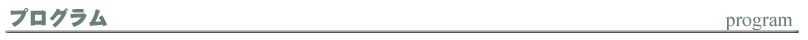
-
-
丂
- 6寧16擔丂嫗墹僾儔僓儂僥儖杮娰43奒僗僞乕儔僀僩丂9:00乣9:52
- 塽妛抧堟嘆
- 嵗挿丗 嫶杮丂塹乮孎杮戝妛堛妛晹晬懏昦堾恄宱惛恄壢乯
- P-A-1丂
- 堦斒廧柉偵偍偗傞挳椡掅壓偲擣抦婡擻掅壓偺娭學偵偮偄偰
- 悰尨丂揟晇乮峅慜垽惉夛昦堾惛恄壢丆峅慜戝妛戝妛堾恄宱惛恄堛妛島嵗乯
- 亂栚揑亃擭楊偺忋徃偲偲傕偵挳妎忈奞偺滊姵棪偑憹壛偡傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丏挳妎忈奞偲擣抦婡擻掅壓傗梷偆偮忬懺偲偺娭楢惈傪巜揈偡傞曬崘偑偁傞堦曽偱丆梷偆偮忬懺偵娭偟偰偼娭楢惈傪斲掕偡傞傕偺傕懚嵼偡傞偺偑尰忬偱偁傞丏挳妎忈奞偵敽偆梷偆偮忬懺偼丆擣抦婡擻掅壓偺慜抜奒偲偟偰丆忣摦偍傛傃峴摦偵懳偡傞摦婡偯偗偺寚擛傪摿挜偲偡傞傾僷僔乕偺崿嵼偑峫偊傜傟傞偑丆偙偆偟偨帇揰偵棫偭偨尋媶偼奆柍偱偁傞丏杮尋媶偱偼丆挳妎忈奞偲擣抦婡擻偍傛傃梷偆偮丆傾僷僔乕偺娭楢傪堦斒寬峃廧柉偵偍偄偰専摙偡傞丏
- 亂曽朄亃2008擭偐傜2009擭偵偐偗偰娾栘寬峃憹恑僾儘僕僃僋僩偵嶲壛偟偨50嵨埲忋偺堦斒寬峃廧柉846柤乮抝惈310柤丆彈惈536柤乯傛傝尋媶嶲壛偺摨堄傪摼偰丆懳徾幰偲偟偨丏僆乕僕僆儊乕僞乕AA乚73A乮RION乯偵傛傝500丆1,000丆2,000Hz偺婥摫挳椡傪應掕偟丆偦偺暯嬒抣傪挳椡偲偟偨丏擣抦婡擻偺昡壙偵偼Mini乚Mental State Examination乮MMSE乯丆傾僷僔乕偺昡壙偵偼Starkstein's apathy scale乮AS乯丆梷偆偮忬懺偺昡壙偵偼Center for Epidemiologic Studies Depression乮CES乚D乯scale傪嫟偵擔杮斉偱巊梡偟偨丏傑偨丆寬峃娭楢QOL傪應掕偡傞偨傔偵丆Short乚Form 36 Health Survey Version 2.0乮SF乚36v2乯傪巊梡偟偨丏擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢偵娭偡傞忣曬偼丆帺婰幃傾儞働乕僩傛傝摼偨丏
丂嶲壛幰傪挳椡偵傛傝25dB枹枮傪挳椡忈奞側偟孮丆25dB埲忋偐傜40dB枹枮傪寉搙擄挳孮丆40dB埲忋傪拞搙埲忋擄挳孮偲3孮偵暘偗丆楢懕検曄悢偼懳墳偺側偄t専掕偱孮娫偺斾妑傪峴偭偨丏
丂傑偨丆挳椡偲MMSE丆CES乚D丆AS傑偨偼SF乚36偺壓埵崁栚偲偺娭學偵偮偄偰偼丆擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢傪嫟曄悢偲偟偰廳夞婣暘愅傪幚巤偟偨丏側偍丆桳堄悈弨偼p亙0.05偵愝掕偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偺幚巤偵愭棫偪丆峅慜戝妛戝妛堾堛妛尋媶壢椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偨丏
- 亂寢壥亃MMSE摼揰偲挳椡偲偺娫偵娭楢惈乮兝亖亅0.141丆t亖亅4.177丆P亙0.001乯傪擣傔傞堦曽丆CES乚D偲偺娫偵偼摨條偺孹岦偼傒傜傟側偐偭偨丏AS偲挳椡偺娫偵偼娭楢惈乮兝亖0.094丆t亖2.434丆P亙0.05乯傪擣傔偨丏傑偨丆挳椡掅壓偼SF乚36偺壓埵崁栚偱偁傞幮夛惗妶婡擻乮兝亖亅0.084丆t亖亅2.165丆P亙0.05乯傗擔忢栶妱婡擻乮惛恄乯乮兝亖亅0.089丆t亖亅2.332丆P亙0.05乯偲傕娭楢惈偑擣傔傜傟偨丏
- 亂峫嶡亃堦斒寬峃廧柉偵偍偄偰挳椡掅壓偼丆MMSE偺掅抣傗AS偺崅抣偲娭楢傪擣傔偨偑丆CES乚D偱偼偦偆偟偨娭楢偼傒傜傟側偐偭偨丏
- P-A-2丂
- 搒巗嵼廧崅楊幰偺帺妎揑側傕偺朰傟偺暘晍偲娭楢梫場媦傃媞娤揑側擣抦婡擻掅壓偲偺娭楢
- 堜摗丂壚宐乮搶嫗搒寬峃挿庻堛椕僙儞僞乕尋媶強乯
- 亂栚揑亃搒巗嵼廧崅楊幰傪懳徾偵丆帺妎揑側傕偺朰傟偺暘晍偲娭楢梫場丆偍傛傃帺妎揑側傕偺朰傟偲媞娤揑側擣抦婡擻偲偺娭楢偵偮偄偰暘愅偟偨丏
- 亂曽朄亃搶嫗搒A嬫嵼廧偺65嵨埲忋偺慡崅楊幰偺偆偪丆4寧偐傜9寧惗傑傟偱丆崅楊幰巤愝偵擖強拞偺幰傪彍偔3827恖傪懳徾偵丆梄憲朄偵傛傞帺婰幃傾儞働乕僩挷嵏傪幚巤偟偨丏傾儞働乕僩偼恖岥摑寁妛揑梫場丆幮夛揑梫場丆寬峃娭楢梫場偵娭偡傞幙栤崁栚偱峔惉偝傟傞丏傾儞働乕僩夞摎幰偺偆偪95恖傪懳徾偵丆惛恄壢堛偵傛傞柺愙偲擣抦婡擻専嵏傪巤峴偟偨丏柺愙偱CDR傪昡壙偟丆擣抦婡擻専嵏偼丆MMSE丆AQT丆WMS乚R偺榑棟揑婰壇丆ADAS Cog偺10扨岅嵞惗丆WAIS 嘨偺椶帡偲晞崋丆TMT A丆TMT B傪巤峴偟偨丏摑寁夝愅偵偼t専掕丆儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅丆廳夞婣暘愅傪梡偄偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼搶嫗搒寬峃挿庻堛椕僙儞僞乕尋媶強偺椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偰峴傢傟偨丏
- 亂寢壥1丗帺妎揑側傕偺朰傟偺暘晍偲娭楢梫場亃
2431恖偐傜桳岠昜傪夞廂偟偨乮夞廂棪63.5亾乯丏帺妎揑側傕偺朰傟偼丆傕偺朰傟偺晄埨乮乽偁側偨偼尰嵼丆傕偺朰傟偵懳偡傞晄埨偼偁傝傑偡偐乿乯偲丆傕偺朰傟偑憹偊偨帺妎乮乽偁側偨偼丆敿擭慜偵斾傋偰丆傕偺朰傟偑憹偊偨偲姶偠傑偡偐乿乯偺2崁栚偱昡壙偟偨丏夝愅偼丆偦傟偧傟偺幙栤崁栚偵寚懝抣偺側偄1508恖丆1096恖傪懳徾偲偟偨丏弌尰昿搙偼丆傕偺朰傟偺晄埨偑67.5亾丆傕偺朰傟偑憹偊偨帺妎偼49.1亾偩偭偨丏扨曄検夝愅偱偼丆傕偺朰傟偺晄埨偼丆彈惈偱偁傞偙偲丆擭楊偑崅偄偙偲丆廇楯偟偰偄側偄偙偲丆僜乕僔儍儖僱僢僩儚乕僋偑彫偝偄偙偲丆庡娤揑寬峃娤偺晄椙丆怱幘姵偺婛墲丆醬捝丆惛恄揑寬峃搙偺晄椙丆梷偆偮丆擔拞偺柊婥丆IADL偺掅壓偲娭楢偟偨丏傕偺朰傟偑憹偊偨帺妎偵偼丆擭楊偑崅偄偙偲丆嫵堢擭悢偑掅偄偙偲丆撈嫃丆廇楯偟偰偄側偄偙偲丆僜乕僔儍儖僱僢僩儚乕僋偑彫偝偄偙偲丆庡娤揑寬峃娤偺晄椙丆偑傫偺婛墲丆怱幘姵偺婛墲丆惛恄揑寬峃搙偺晄椙丆梷偆偮丆擔拞偺柊婥偲娭楢偟偨丏懡廳嫟慄惈傪峫椂偟偰扨曄検夝愅偱桳堄側娭楢傪擣傔偨梫場傪愢柧曄悢搳擖偟偨懡曄検儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅傪峴偭偨丏傕偺朰傟偺晄埨偵偼丆彈惈偱偁傞偙偲丆惛恄揑寬峃搙偺晄椙丆擔拞偺柊婥丆IADL偺掅壓偑丆偦傟偧傟撈棫偵娭楢偟偨丏傕偺朰傟偑憹偊偨帺妎偵偼丆擭楊偑崅偄偙偲丆醬捝丆惛恄揑寬峃搙偺晄椙丆擔拞偺柊婥丆IADL偺掅壓偑丆偦傟偧傟撈棫偵娭楢偟偨丏
- 亂寢壥2丗帺妎揑側傕偺朰傟偲擣抦婡擻偲偺娭楢亃
懳徾幰95恖偺MMSE偺暯嬒揰亇昗弨曃嵎偼28.23亇1.63偱偁偭偨丏CDR亖0乮n亖78乯孮偲CDR亖0.5埲忋乮n亖17乯孮偺MMSE偺暯嬒亇昗弨曃嵎偼偦傟偧傟28.58亇1.33丆26.65亇1.97偱丆CDR亖0.5孮偱桳堄偵掅偐偭偨乮t亖4.930丆p亙0.001乯丏偟偐偟CDR偲帺妎揑側傕偺朰傟偺慽偊偼娭楢偟側偐偭偨丏擭楊丆嫵堢擭悢丆偍傛傃懡曄検夝愅偱桳堄側娭楢傪擣傔偨梫場傪嫟曄検偵搳擖偟偨廳夞婣暘愅偵偍偄偰丆偄偢傟偺擣抦壽戣傕丆帺妎揑側傕偺朰傟偲桳堄側娭楢傪擣傔側偐偭偨丏
- 亂寢榑亃搒巗嵼廧崅楊幰偵偍偄偰丆帺妎揑側傕偺朰傟偼丆惛恄揑寬峃搙偺晄椙丆擔拞偺柊婥丆IADL偺掅壓偲撈棫偵娭楢偡傞偑丆媞娤揑側擣抦婡擻掅壓偲偼娭楢偟側偄丏
- P-A-3丂
- 堦斒惗妶幰偵偍偗傞擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偲偦偺娭楢梫場
- 孎杮丂孿屷乮(撈)崙棫挿庻堛椕尋媶僙儞僞乕挿庻惌嶔壢妛尋媶晹乯
- 亂栚揑亃乽挻崅楊壔幮夛乿傪寎偊傞偲偝傟傞傢偑崙偵偍偄偰丆堦斒偺惗妶幰偺懡偔偑丆崅楊偵側傝擣抦徢側偳偵側傞偙偲傊偺晄埨傪書偊偰偄傞丏偦偙偱杮尋媶偱偼丆堦斒惗妶幰偵偍偄偰丆帺恎偑擣抦徢偵滊姵偡傞偙偲傊偺晄埨傪偳偺掱搙書偄偰偄傞偐丆偍傛傃擣抦徢滊姵偺晄埨偵娭楢偡傞梫場偵偮偄偰柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丏
- 亂懳徾偲曽朄亃懳徾丗堦斒惗妶幰僷僱儖偐傜拪弌偟丆挷嵏嫤椡偺堄巙傪昞柧偟偨20嵨埲忋偺2,500柤傪懳徾偵丆帺婰幃幙栤昜偵傛傞梄憲挷嵏傪2006擭偵幚巤偟丆2,161柤偺桳岠夞摎傪暘愅懳徾偲偟偨丏夞摎偼摻柤偲偟屄恖偑摿掕偱偒傞忣曬偼庢摼偟偰偄側偄丏暘愅懳徾幰偺惈暿偼丆抝惈偑1,101柤丆彈惈偑1,149柤丆晄柧偑1柤偱偁偭偨丏擭楊偼丆20乣39嵨偑755柤丆40乣64嵨偑806柤丆65嵨埲忋偑600柤偱偁偭偨丏
曽朄丗乮1乯擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偺桳柍丗乽彨棃擣抦徢偵側傞偙偲偵偮偄偰偳偺掱搙晄埨偵姶偠偰偄傞偐乿偵偮偄偰丆乽1丗傛偔晄埨傪姶偠傞偙偲偑偁傞乿偐傜乽4丗慡偔晄埨傪姶偠傞偙偲偼側偄乿傑偱偺4審朄偱夞摎傪媮傔丆乽1丆2乿傪乽晄埨偁傝亖1乿乽3丆4乿傪乽晄埨側偟亖0乿偺2抣偵曄姺偟偨丏乮2乯擣抦徢偺抦幆丗擣抦徢偵娭偡傞11崁栚偐傜惓偟偄撪梕偺崁栚偺慖戰傪媮傔丆惓摎悢傪揰悢偲偟偨丏乮3乯夘岇曐尟偍傛傃堛椕惂搙偵懳偡傞枮懌搙丗偦傟偧傟偵偮偄偰乽1丗旕忢偵枮懌偱偒傞乿偐傜乽4丗慡偔枮懌偱偒側偄乿傑偱偺4審朄偱夞摎傪媮傔偨丏乮4乯擣抦徢偲偺娭傢傝丆偍傛傃嵟嬤1擭娫偺庴恌丗偦傟偧傟偵偮偄偰桳柍傪恞偹偨乮乽娭傢偭偨偙偲偑偁傞乿乽庴恌偟偨乿亖1乯乯丏
- 亂寢壥亃懳徾幰偺62.1亾乮1335柤乯偑丆帺恎偺擣抦徢滊姵偵懳偟偰晄埨偑偁傞丆偲夞摎偟偰偄偨丏惈暿偱偼彈惈偵偍偄偰丆傑偨丆擭楊憌偑忋偱偁傞傎偳丆擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偑偁傞幰偺妱崌偑崅偐偭偨乮Mantel乚Haenszel専掕偵偰p亙0.0001乯丏
丂擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偺桳柍傪廬懏曄悢偲偟丆擣抦徢偺抦幆丆夘岇曐尟偵懳偡傞枮懌搙丆堛椕惂搙偵懳偡傞枮懌搙丆擣抦徢偲偺娭傢傝偺桳柍丆嵟嬤1擭娫偺庴恌偺桳柍丆傪撈棫曄悢偲偟偰丆儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅傪峴偭偨丏撈棫曄悢傪嫮惂搳擖偟丆惈偲擭楊偱挷惍偟偨寢壥丆5亾悈弨偵偰桳堄側娭楢偑擣傔傜傟偨曄悢偼埲壓偺捠傝偱偁偭偨乮妵屖撪偼丆僆僢僘斾丗僆僢僘斾偺95亾怣棅嬫娫乯丏夘岇曐尟偵懳偡傞枮懌搙偑掅偄乮1.350丗1.069亅1.706乯丆擣抦徢偲娭傢偭偨偙偲偑偁傞乮1.791丗1.379亅2.143乯丆嵟嬤1擭娫偵庴恌偟偨偙偲偑偁傞乮1.757丗1.373亅2.248乯丏
- 亂峫嶡亃杮尋媶偺寢壥丆擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偼丆擣抦徢偺抦幆傗堛椕惂搙偺枮懌搙偲偼桳堄側娭楢偑擣傔傜傟側偐偭偨偑丆昦堾傪庴恌偟偰偄偨幰偵偍偄偰晄埨偑崅偐偭偨丏偙偺寢壥偐傜丆擣抦徢滊姵偵偮偄偰偺晄埨偼丆昦婥慡斒偵懳偡傞滊姵傊偺晄埨偵嬤偔丆幘姵偲偟偰偺擣抦徢偺抦幆傗丆堛椕傊偺婜懸姶偼丆晄埨偺掅尭偵偁傑傝寢傃偮偄偰偄側偄偙偲偑帵嵈偝傟偨丏堦曽丆擣抦徢偲娭傢偭偨宱尡偑偁傞幰丆夘岇曐尟惂搙偵枮懌姶傪帩偭偰偄側偄幰偵偍偄偰桳堄偵晄埨偑崅偔丆擣抦徢滊姵偵懳偡傞晄埨偼丆庡偵帺恎偑梫夘岇忬懺偵側傞偙偲偵懳偡傞晄埨偲偟偰懆偊傜傟偰偄傞偲峫偊傜傟偨丏
- P-A-4丂
- 擣抦徢崅楊幰偑巤愝擖強傗堛椕婡娭擖堾傪慖戰偡傞攚宨梫場丟嵼戭惗妶偺宲懕傪崲擄偵偝偣傞梫場偵偮偄偰偺傾儞働乕僩偵傛傞専摙
- 庒徏丂捈庽乮擔杮堛壢戝妛榁恖昦尋媶強奨偖傞傒擣抦徢憡択僙儞僞乕乯
- 亂偼偠傔偵亃変乆偼暥晹壢妛徣幮夛楢実尋媶悇恑帠嬈偲偟偰偺乽奨偖傞傒擣抦徢憡択僙儞僞乕乿傪塣塩偟偰偄傞丏憡択椪彴傪宲懕偡傞側偐偱丆摿偵幘昦偑拞摍搙埲忋偲巚傢傟傞帠椺偵偍偄偰丆摉弶偼嵼戭惗妶傪偟偰偄偨傕偺偺丆崅楊幰暉巸巤愝傗惛恄恄宱壢昦彴丆傑偨偼偦偺懠椕梴宆昦彴傊堎摦偡傞帠椺偑嶶尒偝傟傞丏擣抦徢働傾偱偼丆幘昦偺憗婜恌抐丒憗婜帯椕偲偲傕偵丆嵼戭働傾偺宲懕偵塭嬁偡傞梫場偺専摙傕廳梫偱偁傠偆丏崱夞変乆偼丆擔忢揑偵嫤摨妶摦偡傞偙偲偺懡偄抧堟曪妵巟墖僙儞僞乕傗嫃戭夘岇巟墖帠嬈強偺嫤椡傪摼偰丆擣抦徢崅楊幰偑嵼戭働傾偐傜巤愝擖強傗堛椕婡娭擖堾偵傛傞働傾偵堏峴偡傞嵺偺梫場偵偮偄偰丆傾儞働乕僩偵傛傝専摙傪壛偊偨偺偱曬崘偡傞丏
- 亂曽朄亃嵼戭偵傛傞働傾宲懕傪崲擄偵偝偣傞偲巚傢傟傞尨場傪丆偁傜偐偠傔戝梫場偲偟偰嘆拞妀徢忬丆嘇峴摦忈奞丆嘊慡恎忬懺憹埆丆嘋夘岇幰旀楯丒晧扴姶憹戝丆嘍夘岇幰堄梸掅壓丆嘐夘岇幰晄懌丆嘑抧堟惗妶忋偺杸嶤丆嘒尃棙梚岇丒曐岇丆嘓壠壆偺暔棟揑棟桼丆嘔宱嵪揑棟桼偲掕媊偟丆偝傜偵嵶暘壔偟偨40偺彫梫場傪嫇偘偨挷嵏昜傪嶌惉偟偨丏偙傟傪抧堟曪妵巟墖僙儞僞乕傗嫃戭夘岇巟墖帠嬈強偺働傾儅僱乕僕儍乕傗幮夛暉巸巑丆娕岇巘側偳偵攝晍偟丆帺傜偑扴摉偟偨擣抦徢崅楊幰帠椺偵偍偄偰丆嵼戭惗妶偺宲懕傪崲擄偵偝偣偨梫場傪暋悢夞摎偡傞偙偲偲偟偨偆偊偱丆偦偺偆偪嵟戝偺棟桼偲傒傜傟傞梫場傪傂偲偮偩偗慖戰偡傞偙偲偲偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃挷嵏偵偁偨偭偰偼丆挷嵏昜埶棅愭偺摻柤惈傪偼偠傔偲偟偰丆懳徾偲側傞崅楊幰偺摻柤惈傗忣曬偺旈摻娗棟偵偼嵟戝尷棷堄偟偨丏
- 亂寢壥亃乹挷嵏偵偮偄偰乺尰帪揰偵偍偄偰懳徾偼62椺乮嫃戭夘岇巟墖帠嬈強54椺丆抧堟曪妵巟墖僙儞僞乕8椺乯偱偁傞丏夞摎幰偼働傾儅僱乕僕儍乕55椺丏幮夛暉巸巑5椺丏娕岇巘2椺偱偁偭偨丏懳徾擣抦徢崅楊幰偼抝惈23椺乮暯嬒擭楊84.8嵨乯丆彈惈39椺乮暯婥擭楊83.9嵨乯丏恌抐柤偼抝彈偦傟偧傟丆傾儖僣僴僀儅乕昦乮7椺丆17椺乯丆擼寣娗惈擣抦徢乮11椺丆15椺乯丆偦偺懠乮4椺丆7椺乯丆晄柧乮1椺丆0椺乯偱偁偭偨丏嵟崅嵟懡夘岇搙偼抝惈偱梫夘岇3偑8椺丆彈惈偱梫夘岇4偑13椺丏敪徢偐傜擖強丒擖堾偵帄傞婜娫偑偁傞掱搙柧傜偐側38椺慡懱偱丆偦偺暯嬒婜娫偼4.0擭偱偁偭偨丏堎摦愭偼抝惈偱帺戭偐傜夘岇晅偒乮桳椏乯榁恖儂乕儉6椺丆彈惈偱摿暿梴岇榁恖儂乕儉17椺偑傕偭偲傕懡偐偭偨丏
乹攚宨梫場偵偮偄偰乺擣抦徢崅楊幰偑嵼戭惗妶傪宲懕偡傞偙偲偑崲擄偲側傞堦斒揑梫場乮暋悢夞摎乯偲偟偰偼丆嘆拞妀徢忬29.6亾丆嘋夘岇幰旀楯丒晧扴姶憹戝28.4亾丆嘇峴摦忈奞15.8亾偑懡悢傪愯傔偰偄偨乮偦偺懠偼10亾枹枮乯丏偦傟偵懳偟偰丆嵟戝梫場乮扨悢夞摎乯偲偟偰偼丆嘋夘岇幰旀楯丒晧扴姶憹戝33.3亾丆嘊慡恎忬懺憹埆28.1亾丆嘐夘岇幰晄懌10.5亾偑懡悢傪愯傔偰偄偨乮偦偺懠偼10亾枹枮乯丏
- 亂峫嶡亃暋悢夞摎偲偟偰嫇偘傜傟偨梫場偼丆擔乆懳墳偵嬯椂偡傞壽戣偲偟偰峫偊傞偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆丏寬朰傪庡偲偡傞拞妀徢忬偼丆壠懓偵偄偮傕摨偠帠暱傊偺懳墳傪嫮偄傞寢壥偲側傞丏偙傟偑壠懓偺怱棟揑旀暰偵傛傞揔愗偱偼側偄働傾偺尦偲側傝丆擣抦徢崅楊幰偺峴摦忈奞傪憹暆偝偣傞埆弞娐偲側傞偙偲偼婛偵巜揈偝傟偰偄傞丏偦偆偟偨拞偱丆嵼戭惗妶傪嵟廔揑偵崲擄偵偡傞傕偺偼丆壠懓偺怱恎旀暰偲崅楊幰杮恖偺慡恎忬懺偺憹埆偱偁傞丏偙偺抜奒偵偍偄偰偼丆楯椡偑壠懓偵曃嵼偟偨働傾偱偼丆夘岇暉巸揑偵傕堛妛揑偵傕嵼戭惗妶偺宲懕偼崲擄偱偁傠偆丏憗婜敪尒丒憗婜帯椕偵偼偠傑傞擣抦徢働傾偵偼丆嵼戭惗妶偺巟墖偲偲傕偵丆偦偺愭偵偍偄偰傕擣抦徢崅楊幰偲壠懓偵埨慡偲埨怱傪妋曐偱偒傞丆嵼戭奜偱偺愱栧揑働傾乮擖強丒擖堾乯偺廩懌偑昁梫偱偁傠偆丏
- P-A-5丂
- 擣抦徢偺偨傔偺堛椕僒乕價僗偺尰忬傪攃埇偡傞偨傔偺昡壙広搙(MSD-50)偺奐敪
- 埦揷丂庡堦乮搶嫗搒寬峃挿庻堛椕僙儞僞乕尋媶強丆愬戜巗棫昦堾擣抦徢幘姵堛椕僙儞僞乕乯
- 亂栚揑亃杮尋媶偺栚揑偼丆擣抦徢偺偨傔偺堛椕僒乕價僗偺尰忬傪攃埇偡傞偨傔偺昡壙広搙乮Medical Serivices for Dementia乚50items, MSD乚50乯傪奐敪偡傞偙偲偵偁傞丏
- 亂曽朄亃擣抦徢偺堛椕丒曐寬丒暉巸偵廬帠偡傞堛巘丆曐寬巘丆娕岇巘丆惛恄曐寬暉巸巑丆椪彴怱棟媄弍幰偱峔惉偝傟傞嶌嬈僌儖乕僾乮WG乯偱丆擣抦徢偺堛椕偵媮傔傜傟傞婡擻傪壜擻側尷傝拪弌偟丆撪梕傪嬦枴偟偨忋偱30崁栚偺幙栤昜乮MSD乚30乯傪嶌惉偟偨丏杮幙栤昜傪梡偄偰愬戜巗堛巘夛搊榐堛椕婡娭750巤愝傪懳徾偵梄憲朄丒帺婰幃傾儞働乕僩挷嵏傪峴偭偨偲偙傠丆275偺堛椕婡娭偐傜夞摎傪摼乮夞廂棪36.7亾乯丆扵嶕揑場巕暘愅偺寢壥7偮偺愽嵼場巕偑拪弌偝傟偨丏偙偺寢壥傪摜傑偊丆WG偵偍偄偰擣抦徢偺堛椕偵媮傔傜傟傞婡擻偵偮偄偰偝傜側傞専摙傪廳偹丆彮側偔偲傕8偮偺婡擻傪昡壙偡傞偙偲傪憐掕偟偨50崁栚偺幙栤昜乮MSD乚50乯傪嶌惉偟丆搶嫗搒乮斅嫶嬫丆朙搰嬫丆杒嬫乯堛巘夛搊榐堛椕婡娭931巤愝偲搶嫗搒堛椕婡娭埬撪僒乕價僗偱乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞昦堾乿偲偟偰搊榐偝傟偰偄傞255巤愝傪懳徾偵梄憲朄丒帺婰幃傾儞働乕僩挷嵏傪幚巤丆場巕揑懨摉惈傪専摙偡傞偲偲傕偵丆場巕僗僐傾偺儗乕僟乕丒僠儍乕僩傪嶌惉偟偰丆広搙偺桳梡惈傪専摙偟偨丏彯丆杮尋媶偼搶嫗搒寬峃挿庻堛椕僙儞僞乕尋媶強椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偰幚巤偟偨丏挷嵏偍傛傃暘愅偺懳徾偼巤愝偱偁傝丆屄恖忣曬偼庢傝埖偭偰偄側偄丏
- 亂寢壥亃搶嫗搒堛巘夛搊榐堛椕婡娭280巤愝乮夞廂棪30.1亾乯偲乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞昦堾乿92巤愝乮夞廂棪36.1亾乯偐傜夞摎傪摼偨丏夞廂偝傟偨幙栤昜偺偆偪丆MSD乚50偵寚懝抣偑側偔丆偐偮搶嫗搒堛巘夛搊榐堛椕婡娭偱乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞乿偲夞摎偟偨恌椕強178巤愝偲搶嫗搒堛椕婡娭埬撪僒乕價僗搊榐堛椕婡娭偱乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞乿偲怽崘偟偰偄傞昦堾92巤愝偺僨乕僞傪暪偣偨崌寁270偺壓埵僒儞僾儖傪嶌惉偟丆庡場巕朄偵傛傞場巕暘愅傪峴偭偰8場巕傪拪弌偟偨丏場巕晧壸検偺崅偄幙栤崁栚偐傜奺場巕偼埲壓偺傛偆偵柦柤偝傟偨丏戞1場巕丗娪暿恌抐婡擻丆戞2場巕丗抧堟楢実婡擻丆戞3場巕丗恎懱崌暪徢擖堾懳墳婡擻丆戞4場巕丗廃曈徢忬擖堾懳墳婡擻丆戞5場巕丗廃曈徢忬奜棃懳墳婡擻丆戞6場巕丗庡帯堛婡擻丆戞7場巕丗嵼戭堛椕婡擻丆戞8場巕丗廳搙擣抦徢挿婜椕梴婡擻丏堛椕婡娭庬暿偵場巕僗僐傾暯嬒揰偺儗乕僟乕丒僠儍乕僩傪嶌惉偟偰堛椕僒乕價僗偺僾儘僼傿儖傪斾妑偟偨偲偙傠丆乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞昦堾乿偼戞1丆2丆3丆4丆5丆8場巕偱摼揰偑憡懳揑偵崅偔丆乽擣抦徢偺恌椕傪峴偭偰偄傞恌椕強乿偼戞6丆7場巕偱摼揰偑憡懳揑偵崅偄丏偐偐傝偮偗堛擣抦徢懳墳椡岦忋尋廋偵乽嶲壛偟偰偄傞乿恌椕強偲乽嶲壛偟偰偄側偄乿恌椕強傪斾妑偟偨偲偙傠丆嶲壛偟偰偄傞恌椕強偼戞1丆2丆5丆6丆7場巕偱摼揰偑崅偄丏傕偺朰傟奜棃傪傕偮憤崌昦堾偼戞1丆2丆3丆5場巕偱摼揰偑崅偔丆擣抦徢帯椕昦搹傪傕偮扨壢惛恄壢昦堾偼戞4場巕偱摼揰偑崅偔丆椕梴昦搹傪傕偮昦堾偱偼戞8場巕偱摼揰偑崅偄丏
- 亂寢榑亃MSD乚50偺場巕揑懨摉惈偑妋擣偝傟偨丏MSD乚50偼擣抦徢偺偨傔偺堛椕僒乕價僗偺尰忬昡壙偵桳梡偱偁傞丏擣抦徢幘姵堛椕僙儞僞乕偼戞1乣5場巕偺偡傋偰偵偍偄偰戩墇偟偨婡擻傪傕偮偙偲偑婜懸偝傟傞丏
- P-A-6丂
- 抧堟嵼廧崅楊幰偺梷偆偮忬懺傊偺儊僞儃儕僢僋徢岓孮偺塭嬁丟摗尨嫗僗僞僨傿
- 怷愳丂彨峴乮嶄巗偙偙傠偺寬峃僙儞僞乕丆撧椙導棫堛壢戝妛惛恄堛妛島嵗乯
- 亂栚揑亃崅楊幰偺梷偆偮忬懺偵偼丆怱棟幮夛揑側塭嬁偺傒側傜偢恎懱幘姵偺塭嬁傕庴偗傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞偑丆崱夞丆儊僞儃儕僢僋徢岓孮乮埲壓Mets乯偺梷偆偮忬懺偵梌偊傞塭嬁偵偮偄偰専摙偟偨丏
- 亂懳徾亃撈曕壜擻側65嵨埲忋偺抧堟嵼廧崅楊幰偺QOL偲惗妶婡擻偵娭偡傞僐儂乕僩尋媶乮摗尨嫗僗僞僨傿乯偺儀乕僗儔僀儞寬恌乮2007亅2008擭乯嶲壛幰4,427恖偺偆偪丆寚懝抣傪彍偄偨3,796恖乮抝惈1,911恖丆彈惈1,885恖乯傪夝愅懳徾偲偟偨丏
- 亂曽朄亃梷偆偮忬懺偺攃埇偵偼Geriatric Depression Scale抁弅斉乮GDS15乯傪梡偄偨丏偦偺懠丆帺婰幃挷嵏昜丆恎懱寁應丆擣抦婡擻乮MMSE乯丆帟壢専恌偦偟偰寣塼専嵏側偳傪幚巤偟偨丏Mets偺敾掕偵偼崙嵺摐擜昦楢柨乮IDF丆2005乯偺婎弨傪梡偄偨丏憐掕偟偨娭楢場巕奺乆偵偮偄偰擭楊丆惈嵎丆Mets偺桳柍偱曗惓偟偨儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅傪峴偄丆P抣偑0.05枹枮偺傕偺傪拪弌丆嵟廔揑偵16偺場巕亂擭楊丆惈暿丆嫵堢丆悋柊忈奞丆堸庰廗姷丆夁嫀6偐寧偺僗僩儗僗乮攝嬼幰傗巕偳傕偲偺巰暿丆恊愂娭學丆廂擖丆廧嫃廃曈娐嫬乯丆擣抦婡擻丆幮夛揑僒億乕僩乮攝嬼幰丆偦偺懠偺壠懓丆桭恖乯丆帇椡忈奞丆挳椡忈奞丆1擔偺曕峴帪娫乮30暘埲忋偺桳柍乯亃偵峣傝崬傒丆偦傟傜偺挷惍嵪傒僆僢僘斾傪懡廳儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅乮嫮惂搳擖朄乯偱媮傔偨丏側偍丆廬懏曄悢偼GDS15偱6揰埲忋傪梷偆偮忬懺偲偟偰2孮偵暘偗偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃撧椙導棫堛壢戝妛堛偺椣棟埾堳夛偺彸擣傪庴偗偨丏
- 亂寢壥亃梷偆偮忬懺偼GDS15偱14.8亾乮抝惈13.8亾丆彈惈15.8亾乯偵擣傔丆Mets偼16.6亾乮抝惈14.6亾丆彈惈18.7亾乯偱偁偭偨丏Mets偺梷偆偮忬懺偵懳偟偰偺挷惍嵪傒僆僢僘斾偼1.32乮95亾CI丗1.03亅1.68乯偲桳堄側忋徃傪擣傔偨丏懠偺桳堄側挷惍嵪傒婋尟場巕偼丆悋柊忈奞乮2.22丗1.83亅2.70乯丆帇妎忈奞乮2.42丗1.49亅3.95乯丆挳妎忈奞乮1.81丗1.37亅2.40乯丆恊愂娭學偺僩儔僽儖乮1.95丗1.41亅2.70乯丆廂擖尭彮乮1.67丗1.37亅2.04乯丆偦偟偰廧嫃廃曈娐嫬偺埆壔乮1.67丗1.16亅2.40乯偱偁偭偨丏杊屼場巕偱偼丆崅嫵堢楌乮0.78丗0.64亅0.97乯丆堸庰廗姷亂廡2擔埲撪乮0.66丗0.51亅0.86乯丆廡3擔埲忋乮0.61丗0.48亅0.79乯亃丆椙岲側幮夛揑僒億乕僩亂攝嬼幰乮0.69丗0.55亅0.87乯丆偦偺懠偺壠懓乮0.61丗0.50亅0.75乯丆桭恖乮0.53丗0.43亅0.65乯亃丆偦偟偰1擔偺曕峴帪娫偑30暘埲忋乮0.58丗0.43亅0.79乯偱偁偭偨丏側偍丆尰嵼媔墝丆擣抦婡擻丆巆懚帟悢丆巰暿丆擭楊丆偦偟偰惈嵎偵傛傞塭嬁偼擣傔側偐偭偨丏懡廳儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅幃偵傛傞暘椶偺惓摎棪偼85.2亾偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃崱夞偺夝愅偼墶抐挷嵏偺偨傔尷奅偑偁傞偑丆撈曕偱挷嵏嶲壛偑壜擻側崅楊幰偵偍偄偰丆怱憻寣娗宯幘姵偺婋尟場巕偲偝傟傞Mets偼丆懡場巕偵傛傞夝愅偱傕丆梷偆偮忬懺傊偺塭嬁傪傕偨傜偡壜擻惈偑帵偝傟偨丏崱屻丆廲抐尋媶偱偙傟傜傪妋擣偟偨偄丏
-
- 丂
丂
- 6寧16擔丂嫗墹僾儔僓儂僥儖杮娰43奒僗僞乕儔僀僩丂9:52乣10:44
- 塽妛抧堟嘇
- 嵗挿丗 媨塱丂榓晇乮撿嫑徖巗棫備偒偖偵戝榓昦堾乯
- P-A-7丂
- 惉擭屻尒梡恌抐彂偺條幃偵娭偡傞慡崙挷嵏
- 惉杮丂恦乮嫗搒晎棫堛壢戝妛戝妛堾堛妛尋媶壢惛恄婡擻昦懺妛乯
- 亂栚揑亃惉擭屻尒惂搙偑奐巒偝傟偰10擭偑宱夁偟丆條乆側惂搙忋偺栤戣偑巜揈偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傞丏拞偱傕惉擭屻尒怽棫偰偺嵺偵採弌偑昁梫側惉擭屻尒梡恌抐彂偵偮偄偰偼丆悈栰1乯偺巜揈偵偁傞傛偆偵丆杮棃朄棩揑敾抐偱偁傞傋偒椶宆傪丆帠幚忋恌抐彂嶌惉幰偵敾抐傪媮傔傞傛偆側崁栚偑嵟崅嵸敾強嶌惉偺條幃偵娷傑傟偰偍傝丆栤戣偑巜揈偝傟偰偄傞丏傑偨丆奺壠掚嵸敾強偱條幃偵曄峏偑壛偊傜傟丆抧堟娫偱庤懕偒偵偽傜偮偒傪惗偠偰偄傞偙偲傕栤戣偲側偭偰偄傞丏偙偺偨傔丆崱夞傢傟傢傟偼傛傝椙偄恌抐彂嶌惉偺婎慴帒椏偲偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰丆尰嵼慡崙偺壠掚嵸敾強偱梡偄傜傟偰偄傞惉擭屻尒梡恌抐彂傪斾妑専摙偟偨丏
- 亂曽朄亃暯惉22擭偵慡崙31偐強偺庡梫壠掚嵸敾強偵埶棅偟丆偆偪29偐強偐傜恌抐彂偺採嫙傪庴偗婰嵹崁栚偺廤寁傪峴偭偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮挷嵏偼捠忢攝晍偝傟偰偄傞恌抐彂條幃偺専摙偱偁傞偙偲偐傜椣棟揑栤戣偼惗偠側偄丏
- 亂寢壥亃29偐強偡傋偰偺壠掚嵸敾強偱嵟崅嵸敾強嶌惉偺恌抐彂條幃偵側偄崁栚傪撈帺偵晅偗壛偊偰偄偨丏偦偺撪栿偲偟偰偼丆1乯JCS側偳堄幆忈奞偺桳柍偵娭偡傞忣曬丆2乯MRI傗CT偺強尒側偳媞娤揑専嵏強尒丆3乯夵掶斉挿扟愳幃娙堈抦擻専嵏傗MMSE側偳偺抦擻専嵏丆4乯寁嶼椡丆棟夝椡丆婰壇側偳偺擣抦婡擻丆5乯堏摦丆怘帠丆攔煏側偳偺惗妶婡擻丆6乯夞暅壜擻惈側偳偵娭偡傞崁栚偱偁偭偨丏晅偗壛偊傜傟偰偄傞昿搙偑崅偐偭偨崁栚偼丆乽夵掶斉挿扟愳幃娙堈抦擻専嵏乿26偐強丆乽懠恖偲偺堄巚慳捠乿26偐強丆乽抦擻専嵏乮IQ乯乿23偐強丆乽乮慗墑惈乯怉暔忬懺乿20偐強丆乽尒摉幆忈奞乿19偐強丆乽婰壇忈奞乿17偐強丆乽夞暅偺壜擻惈乿16偐強丆乽寁嶼椡乿15偐強偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃奺壠掚嵸敾強偑條乆側崁栚傪撈帺偵晅偗壛偊偰偄傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丏偙偺傛偆側崁栚捛壛偵帄偭偨宱堒偼晄柧偱偁傞偑丆恌抐彂偐傜摼傜傟傞忣曬偵偙傟偩偗偺偽傜偮偒偑偁傟偽丆寢壥偲偟偰椶宆偺敾抐偵堘偄偑惗偠傞偙偲傕梊憐偝傟丆杮棃慡崙堦棩偺婎弨偵懃偭偰恑傔傞傋偒惉擭屻尒惂搙偺庯巪偐傜偡傟偽丆栤戣偑偁傞偲偄傢偞傞傪摼側偄丏傑偨丆堦晹偺恌抐彂偵偼丆乽擣抦偺榗傒乿乽嬻憐暼丒嫊尵暼乿乽旕幮岎惈乿側偳偺堄巚擻椡敾掕偲娭楢偺敄偄崁栚偑晅偗壛偊傜傟偰偄傞椺傕偁傝丆愱栧堛偺懁偐傜偺採尵偑昁梫偲峫偊傜傟偨丏
丂怽棫偰偺嵺偵丆昁偢偟傕偙偺條幃傪梡偄傞昁梫偼側偄偲偝傟偰偄傞偑丆愱栧堛埲奜偑婰嵹偡傞応崌偼丆偙偺恌抐彂傪梡偄丆恌抐彂偺崁栚偵増偭偰姵幰偺恌嶡丆忣曬廂廤傪恑傔傞偙偲偑懡偄偲峫偊傜傟傞丏偙偺偨傔昁梫側忣曬偵峣偭偰丆旕愱栧堛偱傕婰嵹偱偒傞傢偐傝傗偡偄條幃傪梡堄偡傞偙偲偱丆傛傝墌妸偱惓妋側惉擭屻尒惂搙偺塣梡偑壜擻偵側傞偲峫偊傜傟傞丏崱屻偼丆朄棩壠偲愱栧堛偺嫤摥偺傕偲丆1乯偦傟偧傟偺壠掚嵸敾強偑壛偊偨曄峏偲偦偺懨摉惈傪嵞専摙偟丆2乯怽棫偰昿搙偺崅偄幘姵偺徢忬偱敾抐擻椡偵娭楢偡傞傕偺傪拪弌偡傞嶌嬈傪恑傔丆慡崙堦棩偺恌抐彂條幃傪嶌惉偡傞偙偲偑昁梫偲峫偊傜傟偨丏
- 亂嶲峫暥專亃1乯悈栰丂桾丏惉擭屻尒偵娭偡傞惛恄娪掕丆尰忬偲壽戣丏榁擭惛恄堛妛嶨帍21丗747乚755丆2010.
�
- P-A-8丂
- 傾億儕億抈敀E堚揱巕4傾儗儖偲偆偮偲偺娭學偵偍偗傞専摙
- 栰悾丂恀桼旤乮拀攇戝妛戝妛堾恖娫憤崌壢妛尋媶壢乯
- 亂栚揑亃崅楊幰偺惛恄幘姵偺拞偱廳梫側壽戣偲偟偰嫇偘傜傟傞偺偼丆偆偮昦偲傾儖僣僴僀儅乕昦乮AD乯傪偼偠傔偲偡傞擣抦徢偱偁傞丏AD偺婋尟場巕偺傂偲偮偲偟偰妋棫偟偰偄傞偺偑傾億儕億抈敀E堚揱巕4傾儗儖乮ApoE4乯偱偁傞丏偙偺丂ApoE4丂偑崅楊幰偺偆偮昦偲傕娭楢偡傞偐斲偐偵偮偄偰10梋擭娫偵傢偨傝専摙偝傟偰偒偨偑丆巀斲椉榑偑偁偭偰寢榑偑摼傜傟偰偄側偄丏偦偙偱杮尋媶偱偼丆堬忛導棙崻挰偺廧柉傪懳徾偵挷嵏傪幚巤偟偰丆ApoE4偲偆偮昦偲偺娭楢傪専摙偟偨丏
- 亂曽朄亃懳徾偼2001擭5寧1擔帪揰偺堬忛導棙崻挰偺65嵨埲忋偺廧柉3083柤偱偁傞丏挷嵏偼2抜奒偱幚巤偟偨丏1師挷嵏偼2001擭12寧偐傜2002擭4寧偺娫偵幚巤偟偨丏挷嵏崁栚偼婎杮懏惈偲偟偰擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢丆尰嵼偺寬峃忬懺偍傛傃傾億儕億抈敀E堚揱巕宆偺専嵏傪峴側偭偨丏偆偮婥暘偺昡壙偵GDS傪梡偄偨丏庡娤揑側傕偺朰傟偺帺妎偺昡壙偵DECO傪梡偄偨丏ADL偺昡壙偵N乚ADL傪梡偄偨丏擣抦婡擻偺昡壙偵乽僼傽僀僽僐僌乿偲柦柤偟偨廤抍僗僋儕乕僯儞僌僥僗僩僶僢僥儕乕傪奐敪偟梡偄偰抦揑惓忢丆MCI丆擣抦徢偺恌抐傪峴側偭偨丏嵟廔揑側偆偮婥暘偺昡壙偺偨傔偵2002擭4寧偐傜7寧偺娫偵2師挷嵏傪幚巤偟偨丏PAS偲偄偆崅楊幰偺擣抦徢丆偆偮昦偍傛傃擼懖拞傪恌抐偱偒傞峔憿壔柺愙偺僗働乕儖傪梡偄偨丏嵟廔揑偵偼惛恄壢堛巘偑DSM乚嘨乚R偺恌抐婎弨偵偺偭偲偭偨Major Depressive Episode乮MDE乯偐斲偐恌抐偟偨丏嶲壛幰偺拞偱丆GDS偱偼6揰埲忋偱偁偭偨偑丆PAS偵偰MDE偱偼側偄偲敾掕偝傟偨幰偵偼Depressive symptoms cases乮DSC乯偲柦柤偟偨恌抐傪峴側偭偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼拀攇戝妛椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偰峴側傢傟偰偍傝丆懳徾幰偵偼岥摢偲暥彂偵傛傞愢柧傪峴側偄丆摨堄傪庢摼偟偨丏僨乕僞娗棟偼ID傪巊梡偡傞側偳屄恖忣曬偺曐岇偵棷堄偟偨丏
- 亂寢壥亃堬忛導棙崻挰偺懳徾廤抍3,083柤偺偆偪丆嵟廔揑偵偼1619柤偑1師挷嵏偵嶲壛偟偨丏擣抦徢偱側偔丆ApoE堚揱巕宆専嵏傪庴偗丆寚懝抣偺側偄1師挷嵏嶲壛幰偼738柤偱偁偭偨丏2師挷嵏嶲壛幰738柤偵偍偄偰冊2専掕偲t専掕傪梡偄偰ApoE4偲偺娭楢傪専摙偟偨寢壥丆MCI乮冊2亖7.25丆df亖1丆p亖0.009乯偵偍偄偰桳堄嵎偑傒傜傟偨丏ApoE4偼丆偆偮婥暘乮婥暘惓忢丆DSC丆MDE乯偲偺娫偵娭楢偑傒傜傟側偐偭偨偑丆MCI偲偺娫偱娭楢偑傒傜傟偨丏儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅偺寢壥丆DSC偲娭楢偟偨崁栚偼丆惈暿乮OR亖2.53丆95亾CI丗1.33亅4.79乯丆嫵堢擭悢乮OR亖0.87丆95亾CI丗0.79亅0.95乯丆N乚ADL崌寁揰悢乮OR亖0.75丆95亾CI丗0.63亅0.89乯偍傛傃MCI乮OR亖1.95丆95亾CI丗1.21亅3.14乯偱偁偭偨丏MDE偲娭楢偡傞崁栚偼側偐偭偨丏傛偭偰ApoE4偼丆DSC偲MDE偺椉曽偲娭楢偟側偐偭偨丏
- 亂峫嶡亃杮尋媶偱偼ApoE4偑偆偮乮DSC丆MDE乯偺婋尟場巕偱偼側偐偭偨丏廬棃偺娭楢偁傝偲偄偆尋媶寢壥偲偺憡堘偼丆嬤擭拲栚偝傟偰偄傞MCI偺恌抐傪峴側偄丆婛懚偺尋媶傛傝擣抦婡擻乮抦揑惓忢丆MCI丆擣抦徢乯偲偆偮婥暘乮婥暘惓忢丆DSC丆MDE乯傪尩枾偵恌抐偟偰専摙偟偨偨傔偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丏崱夞丆夝愅偵壛偊偨MCI偼ApoE4丆DSC偲娭楢偑傒傜傟偨丏崱屻丆偙偺MCI偑ApoE4偲偆偮乮DSC乯偲偺娫偵丆偳偺傛偆側塭嬁傪媦傏偟偰偄偨偺偐柧傜偐偵偟偨偄丏
- P-A-9丂
- 崅楊幰偵偍偗傞巰惗娤偲偦偺娭楢場巕偵偮偄偰
- 搉绯丂帄乮嵅夑戝妛堛妛晹惛恄堛妛島嵗乯
- 亂栚揑亃廆嫵丆揘妛丆偁傞偄偼巰偺弨旛嫵堢偱偼丆巰偲惓柺偐傜岦偒崌偆偙偲偑丆傛傝傛偔惗偒傞偙偲偵宷偑傞偲偄偆峫偊偑崻掙偵偁傞丏崅楊幰偑丆偳偺傛偆偵巰傪堄幆偟丆偦傟傪偳偺傛偆偵惗偵斀塮偝偣偰偄傞偺偐傪抦傞偙偲偼廳梫偱偁傞丏庻柦偺娤揰偐傜丆崅楊幰偵偍偗傞寬峃偺堐帩偲巰偺庴梕偼昞棤堦懱偺栤戣偲峫偊傞偐傜偱偁傞丏杮尋媶偱偼丆崅楊幰偺巰惗娤傪挷傋丆偦傟偑惈傗擭楊丆惗偒偑偄傗抦揑擻椡偲偳偺傛偆側娭學偵偁傞偺偐傪扵嶕揑偵挷傋傞丏
- 亂椣棟揑攝椂亃嵅夑戝妛偺椣棟埾堳夛偱彸擣傪庴偗丆嶲壛幰偐傜偼暥彂偵傛傞摨堄傪摼偨丏
- 亂曽朄亃挷嵏懳徾幰丗傕偺朰傟寬恌乮擣抦徢桳昦棪挷嵏乯偵嶲壛偟偨埳枩棦巗崟愳挰嵼廧偺崅楊幰偱丆抝惈150柤丆彈惈249柤丆暯嬒擭楊偼76亇6.7嵨丏挷嵏昜丗6崁栚傪4審朄偱夞摎偡傞巰惗娤幙栤巻偼丆挊幰偑拞懞丒堜忋乮2001乯傪婎偵嶌惉偟偨傕偺偱丆巰屻懚懕偲惗偺幏拝偺2場巕偱峔惉偝傟偰偄偨丏巰偲娭楢偡傞宱尡乮埲壓丆巰宱尡乯偼5崁栚傪2審朄偱夞摎偟偨丏惗偒偑偄枮懌搙幙栤巻乮尨壀丆2004乯偼10崁栚傪4審朄偱夞摎偡傞傕偺偱丆埨掕枮懌偲愊嬌枮懌偺2場巕偱惉偭偰偄偨丏偙偺懠偵傕丆MMSE傪偼偠傔偲偡傞悢庬椶偺怱棟専嵏傗嫵堢擭悢傗昦楌摍偺挳庢丆恌嶡偑峴傢傟偨丏庤懕偒丗挷嵏偼2009擭8寧偐傜梻擭10寧偺娫偵廡1側偄偟2夞偢偮丆挰撪奺嫃廧嬫偺岞柉娰偱峴傢傟偨丏嶲壛幰偼梊掕偝傟偨帪娫偵棃娰偟丆奺乆丆婰擖朄偺愢柧傪庴偗偨屻丆幙栤偵夞摎偟偨丏
- 亂寢壥偲峫嶡亃夞摎偵寚懝抣偺側偄373柤傪暘愅懳徾偲偟偨丏擭楊乮75嵨埲忋乛枹枮乯偲惈暿偱奺曄悢偵懳偟偰暘嶶暘愅傪峴偭偨丏巰屻懚懕偱偼惈暿偵丆巰宱尡偱偼擭楊偵奺乆庡岠壥偑擣傔傜傟偨丏埨掕枮懌偱偼惈暿偍傛傃岎屳嶌梡偑桳堄偱偁偭偨丏愊嬌枮懌偱偼惈暿偲擭楊偑偲傕偵桳堄偱偁偭偨丏偙傟傜偼丆乮1乯彈惈偺曽偑偁偺悽傪峬掕揑偵懆偊偰偄傞偙偲丆乮2乯抝惈偺曽偑惗妶偱偺枮懌姶偑崅偔丆傑偨丆崅擭楊偱傛傝崅偔側偭偰偄傞偺偵懳偟丆彈惈偼崅擭楊偱掅偔側偭偰偄傞偙偲丆乮3乯廃埻偵擣傔傜傟偰偄傞偲偄偆姶妎傗愊嬌惈偵偍偗傞枮懌姶偼丆抝惈偑崅偔丆傑偨崅擭楊偱傛傝崅偔側傞丆偺3揰傪帵偟偰偄傞丏墑柦帯椕偺惀旕傗怉暔忬懺偺懆偊曽傪栤偆惗偺幏拝偱偼丆擭楊傗惈偵傛傞堘偄偼側偐偭偨丏師偵丆撈棫曄悢偲側傞場巕傪丆偦偺暯嬒抣偱崅掅孮偵暘偗丆擭楊偲惈暿傪梫場偵壛偊偨忋偱暘愅傪峴偭偨丏乮4乯巰屻懚懕偺崅掅偵偍偄偰丆惗偺幏拝偱桳堄嵎偑弌偨偑丆埨掕枮懌偲愊嬌枮懌偱偼桳堄嵎偑側偐偭偨丏偮傑傝丆偁偺悽偺峬掕偺嫮偝偼丆惗傊偺偙偩傢傝傊偺嫮偝偲楢側傞偙偲傪堄枴偡傞偑丆惗妶偺枮懌姶傗愊嬌惈偲偼捈愙偵偼娭學偟側偐偭偨丏乮5乯巰宱尡偺崅掅偱偼丆巰屻懚懕偵桳堄嵎偑弌偨丏偙傟偼丆懠幰偺巰傪宱尡偡傞傎偳丆偁偺悽偵峬掕揑偵側傞偙偲傪帵嵈偟偰偄傞丏側偍丆嫵堢擭悢偍傛傃MMSE偲巰惗娤場巕偲偺娫偵偼壗傕尒偄偩偣側偐偭偨丏
丂崱屻偼丆巰惗娤偲擔忢偵姶偠傞晄埨傗嫲晐偲偺娭學傪専摙偡傞昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丏埲慜偵峴傢傟偨摨挰偺惗偒偑偄枮懌搙偺尋媶偱偼丆彈惈偺曽偑摼揰偼崅偐偭偨丏偙傟偼僒儞僾儖悢傗嫃廧抧嬫偺堘偄偑塭嬁偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丏
- P-A-10丂
- 帺摦幵塣揮柶嫋峏怴帪偺崅楊幰偺擣抦婡擻偲塣揮忬嫷
- 摗揷丂壚抝乮栚敀戝妛曐寬堛椕妛晹丆宑滀媊弇戝妛堛妛晹惛恄丒惛恄壢妛嫵幒丆拀攇戝妛戝妛堾恖娫憤崌壢妛尋媶壢乯
- 亂栚揑亃帺摦幵塣揮柶嫋傪曐桳偡傞崅楊幰偺憹壛偵敽偄丆崅楊幰偺塣揮偵傛傞帠屘偑憹壛偟偰偄傞丏偦偺懳嶔偺堦娐偲偟偰丆2009擭6寧偐傜廬棃偺崅楊幰島廗偵壛偊丆島廗梊旛専嵏乮擣抦婡擻専嵏乯偑幚巤偝傟偰偄傞丏偙傟偵傛傝擣抦婡擻偑尠挊偵掅壓偟偰偄傞幰偼堦掕偺忦審偱柶嫋傪峏怴偱偒側偄偙偲偲側傝丆奐巒屻1擭偱庢傝徚偟張暘傪庴偗偨幰偼28柤偱偁偭偨丏偙偺懳嶔偼懠崙偵椺傪傒側偄惌嶔偱偁傝丆堦掕偺岠壥偑婜懸偝傟傞偑丆幚嵺偵懡彮偲傕擣抦婡擻偺掅壓傪擣傔傞崅楊幰偑偳偺傛偆側塣揮忬嫷偵偁傞偺偐偼柧傜偐偱偼側偄丏偦偙偱杮尋媶偱偼丆塣揮柶嫋偺峏怴帪偵75嵨埲忋偱偁傞崅楊幰偵丆塣揮忬嫷摍偵娭偡傞傾儞働乕僩傪幚巤偟丆擣抦婡擻傗擭楊偵傛傝塣揮忬嫷偵嵎堎傪擣傔傞偐傪挷嵏偟偨丏
- 亂曽朄亃挷嵏応強偼24搒晎導偺寈嶡杮晹偑巜掕偟偨帺摦幵嫵廗強偱偁傞丏杮尋媶偼2009擭11寧丂偵幚巤偝傟偨寈嶡挕岎捠嬊偵傛傞乽塣揮忬嫷偵娭偡傞傾儞働乕僩乿傪捠偠偰摼傜傟偨僨乕僞傪嫋壜傪摼偰夝愅偟偨傕偺偱偁傞丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼島廗梊旛専嵏傪庴尡偟偨幰偺偆偪丆傾儞働乕僩挷嵏偵偮偄偰嫤椡偺摨堄偑摼傜傟偨幰傪懳徾偲偟偰丆島廗廔椆屻偵傾儞働乕僩傪攝晍偟丆夞摎傪帺屓婰擖偟偰傕傜偭偨丏
- 亂寢壥亃4299恖乮抝惈3401恖丆彈惈890恖乯偐傜夞摎傪摼偨丏島廗梊旛専嵏偺寢壥乮帺屓夞摎乯偼戞1暘椶乮婰壇椡丆敾抐椡偑掅壓偟偰偄傞幰乯338恖丆戞2暘椶乮婰壇椡丆敾抐椡偑彮偟掅偔側偭偰偄傞幰乯1216恖丆戞3暘椶乮婰壇椡丆敾抐椡偵怱攝偺側偄幰乯2409恖偱偁偭偨丏戞1暘椶偵側偭偨幰偼奺擭楊憌偵摨偠傛偆偵暘嶶偟偰偄偨偑丆戞2暘椶偵側偭偨幰偼擭楊憌偑崅偄傎偳憹壛偡傞孹岦偵偁偭偨丏堦曽丆戞3暘椶偼擭楊憌偑崅偄傎偳尭彮孹岦偵偁偭偨丏傑偨丆暘椶偵傛偭偰塣揮忬嫷偵嵎偑偁傞偐傪僋儘僗廤寁偱専摙偟偨偲偙傠丆1乯塣揮昿搙偲暘椶偵偼柧傜偐側娭學偼側偐偭偨丏2乯塣揮偵懳偡傞帺怣偲暘椶偵傕柧傜偐側娭學偼側偐偭偨丏3乯塣揮偟偰偄偰婋側偄偲巚偭偨偙偲偲暘椶偲偺娫偵偼娭學偑擣傔傜傟偨丏偝傜偵丆帺暘偺塣揮擻椡偵偮偄偰偼丆帺怣偑偁傞偲夞摎偟偨幰偲晛捠偺崅楊幰偲摨偠偔傜偄偱偁傞偲夞摎偟偨幰偼崌寁偱97亾偵偺傏偭偨丏
- 亂峫嶡亃帺恎偺塣揮擻椡偵偮偄偰偼丆暘椶偵偐偐傢傜偢憡墳偺帺怣傪帩偭偰偄傞崅楊幰偑懡偄偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丏傑偨丆塣揮昿搙偲暘椶偵傕娭學偑側偐偭偨偙偲偐傜丆擣抦婡擻偑掅壓偟偰傕帺恎偺塣揮擻椡傪崅偔尒愊傕傝丆塣揮傪宲懕偟偰偄傞崅楊幰偑偄傞偙偲偑梊應偝傟偨丏偙偺揰偵偮偄偰偼丆擣抦婡擻偺掅壓偵傛傝僙儖僼儌僯僞儕儞僌婡擻偑廫暘偱側偄応崌偑偁傞偙偲傕峫偊傜傟偨丏崱屻丆崅楊柶嫋曐桳幰偼偝傜偵憹壛偡傞偙偲偑梊應偝傟丆崅楊柶嫋曐桳幰偺偝傜側傞幚懺挷嵏偲丆埨慡惈岦忋傊偺懳墳偑昁梫偲峫偊傜傟傞丏
- P-A-11丂
- 夘岇巤愝偵偍偗傞擣抦徢堛椕偲抧堟楢実
- 媑懞丂撝巕乮曻憲戝妛戝妛堾乯
- 亂栚揑亃枹慭桳偺彮巕崅楊壔幮夛偺傢偑崙偵偍偄偰擣抦徢姵幰偼媫憹偺堦搑傪扝傝丆擣抦徢偵懳墳偟偨堛椕丒夘岇僒乕價僗偺奼廩丆婛懚帒尮偺桳岠妶梡丆抧堟偵偍偗傞楢実嫮壔偼媔嬞偺壽戣偱偁傞丏壽戣払惉偵岦偗桳岠嶔傪島偠傞偵偼丆尰忬攃埇偑媫柋偱偁傞偨傔丆擣抦徢偵娭傢傞堛椕丒夘岇巤愝傪懳徾偵慡崙婯柾偺墶抐挷嵏傪幚巤偟丆幚懺攃埇傪帋傒偨丏
- 亂曽朄亃6,071偺昦堾偲20,000偺夘岇巤愝偐傜柍嶌堊拪弌偟偨2,200昦堾偲5,000巤愝偵挷嵏昜傪憲晅偟丆暯惉21擭9寧帪揰偺巤愝奣嫷偲暯惉20擭搙偺擣抦徢姵幰偺幚懺傪恞偹偨丏夞廂偲擖椡丒廤寁嶌嬈屻丆巤愝庬枅偺姵幰摿惈丆擖強宱楬丆堛椕偲夘岇偺楢実忬嫷摍偵偮偄偰暘愅偟偨丏挷嵏昜偺偆偪丆椪彴屄恖昜偱偼丆擭楊丆ADL丆擣抦徢帺棫搙丆BPSD摍傪丆慡懱昜偱偼丆擖堾丒擖強擔悢側偳偺懠丆働傾偺岺晇傗崲傝帠側偳偵娭偡傞帺桼婰嵹偺愝栤傪愝偗偨丏崱夞偼丆夘岇巤愝偵偍偗傞擣抦徢堛椕傗抧堟偲偺楢実忬嫷傪拞怱偵曬崘偡傞丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮挷嵏偼拀攇戝妛椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偰峴傢傟偨丏挷嵏偺幚巤偵摉偨偭偰偼屄恖忣曬偺曐岇傪尩庣偟丆忣曬偺庢傝埖偄偵偼嵶怱偺拲堄傪暐偭偨丏
- 亂寢壥亃2010擭12寧傑偱偵丆662昦堾偲1,516夘岇巤愝偐傜偺夞摎偑廤傑傝丆堛椕丒夘岇巤愝偲傕偵夞廂棪偼30亾偵払偟偨丏屄恖昜偼堛椕巤愝偐傜偼3,800恖暘丆夘岇巤愝偐傜偼2,622恖暘偑廤傑偭偨丏埲壓丆夘岇帠嬈強偐傜偺夞摎寢壥偺奣梫傪曬崘偡傞丏傑偢丆夘岇巤愝擖強幰偺擣抦徢偺帺棫搙偱偁傞丏擣抦徢偺廳搙乮擣抦徢帺棫搙嘩偲M乯偺曽偑愯傔傞妱崌偼丆摿暿梴岇榁恖巤愝乮摿梴乯丆榁恖曐寬巤愝乮榁寬乯丆僌儖乕僾儂乕儉乮GH乯偵偍偄偰丆偦傟偧傟39亾丆26亾丆22亾偱偁傝丆拞摍搙埲忋乮擣抦徢帺棫搙嘨a埲忋乯偺擖強幰偑愯傔傞妱崌偼丆偦傟偧傟丆85亾丆81亾丆64亾偱偁偭偨丏師偵夘岇帠嬈強偲擣抦徢堛椕婡娭偲偺楢実偱偁傞丏乽擣抦徢堛椕偺懳墳偱崲偭偰偄傞乿偲夞摎偟偨夘岇巤愝偼74亾偵偺傏傞偑丆憡択偱偒傞擣抦徢愱栧堛偺桳柍偑乽偁傞乿偲夞摎偟偨巤愝偼22亾偵偲偳傑偭偨丏傑偨丆抧堟偺懡怑庬娫偺夛崌偑乽偁傞乿偲夞摎偟偨巤愝偼58亾偱丆乽掕婜揑偵偁傞乿偲偺夞摎偼18亾偱偁偭偨丏擖強宱楬傪傒傞偲丆懠偺夘岇巤愝偐傜偺擖強幰偑丆摿梴丆榁寬丆GH偱偦傟偧傟40亾丆14亾丆26亾傪愯傔丆偦偺偆偪6亾丆8亾丆10亾偑摨庬偺巤愝偐傜偺擖強偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃擣抦徢愱栧堛椕婡娭偲偺楢実傪桳偡傞巤愝偼栺2妱偱偁傝丆擣抦徢愱栧堛椕傊偺傾僋僙僗偑擄偟偄忬嫷偑帵嵈偝傟偰偄傞丏傑偨丆擣抦徢崅楊幰偵偲偭偰娐嫬偺曄壔偼朷傑偟偔側偄偲巚傢傟傞傕偺偺丆夘岇巤愝娫偵偍偗傞揮強偺幚懺傕帵嵈偝傟偨丏帺桼夞摎偺拞偱傕乽擣抦徢偵摿壔偟丆僼儖僗僥乕僕偵懳墳偱偒傞巤愝傪嶌傞乿偲偄偆採尵偑偁偭偨偑丆擣抦徢崅楊幰偺摿惈偲僯乕僘傪摜傑偊偨嫃応強偺憂愝偼崱屻偺廳梫側壽戣偲側傞偩傠偆丏傑偨丆抧堟楢実巟墖偵傛傝嵼戭暅婣偵惉岟偟偨帠椺傕曬崘偝傟偰偍傝丆崱屻偼擣抦徢愱栧堛椕偺嫙媼憹偑朷傑傟傞偲嫟偵丆擣抦徢偺恖傪抧堟慡懱偱巟偊傞幮夛偺幚尰偵岦偗偨曽嶔偺奼廩偑朷傑傟傞丏
- P-A-12丂
- 擣抦徢慡崙桳昦棪挷嵏尋媶偵嶲壛偟偰尒偊偰偒偨偙偲丟忋墇巗傕偺傢偡傟梊杊寬峃挷嵏傛傝乮戞堦曬乯
- 愳幒丂桪乮乮堛乯崅揷惣忛夛崅揷惣忛昦堾丆乮堛乯忢怱夛愳幒婰擮昦堾乯
- 亂栚揑亃傢偑崙偺挻崅楊幮夛偵偍偗傞擣抦徢懳嶔偼崙柉揑壽戣偱偁傞丏巹嫟尋媶僾儘僕僄僋僩偼忋墇巗偲嫟摨偱乽H22擭搙慡崙桳昦棪挷嵏尋媶亅憤妵戙昞幰挬揷棽乿偵嶲壛偟忋墇巗恖岥204,193恖丆崅楊幰恖岥53,171恖乮H 21擭10寧1擔尰嵼乯偺拞偐傜980恖傪懳徾偵摑堦偟偨曽幃偱桳昦棪挷嵏傪幚巤偟偨丏摨帪偵夘岇曐尟偺庡帯堛堄尒彂偺忣曬奐帵傪摼偰挷嵏暘愅傪峴偄丆忋墇巗偺擣抦徢幰悢偲娭學彅婡娭偺楢実偵傛傞堛椕丒暉巸僒乕價僗採嫙傪専摙偡傞丏
- 亂曽朄亃懳徾幰偼H21擭10寧1擔尰嵼丆忋墇巗嵼愋65嵨埲忋偺53,171柤乮抝惈21,802柤乛彈惈31,369柤乯偺廧柉婎杮戜挔偐傜柍嶌堊慖弌偟偨丏撪栿偼7奒媺乮65乣69嵨丆埲崀94嵨傑偱5嵨偛偲偵嬫暘丆95嵨埲忋乯偲偟丆懳徾幰偼奺奒媺偐傜140柤乮抝彈奺70柤乯崌寁980柤偱偁傞丏懳徾幰偵偼嫤椡埶棅彂偲摨堄彂偵傛傝摨堄偺忋柺愙丒朘栤偵傛傞堦師挷嵏丆擇師挷嵏傪幚巤偟偨丏堦師挷嵏偼忋墇抧堟曪妵巟墖僙儞僞乕怑堳乮帠慜尋廋廔椆乯偑幚巤偟偨丏敾掕婎弨偼CDR0.5埲忋丆傑偨偼MMSE26揰埲壓傪乽擣抦徢偺媈偄乿偲偟丆偦偺懳徾幰偐傜嵞搙摨堄傪摼偰擇師挷嵏傪幚巤偟偨丏偦偟偰惛恄壢堛巘偺愱栧揑恌嶡暲傃偵嘆榁擭婜偆偮広搙乮抁弅擔杮斉乯亅GDS亅S乚J嘇榁擭婜惛恄忈奞昡壙僗働乕儖乮PAS乯嘊榑棟婰壇嘥乮WMSR棟榑A乯傪巤峴偟丆摨堄偺忋寣塼惗壔妛専嵏偲MRI専嵏傪峴偭偨丏傑偨慡懳徾幰偺夘岇曐尟桳擣掕幰偵丆慡崙挷嵏崁栚嘆夘岇搙嘇擔忢惗妶帺棫搙嘊恌抐柤偲丆擣抦徢傪桳偡傞偑夘岇曐尟枹棙梡幰偵偮偄偰嘋庡帯堛偺愱栧壢偲懠壢偲偺娭楢嘍擣抦徢偺拞妀丒廃曈徢忬丆懠偺惛恄丒恄宱徢忬丆恎懱忬懺嘐惗妶婡擻偲僒乕價僗暲傃偵堛椕丒暉巸僒乕價僗傊偺堄尒偲撪梕摍傪墈棗挷嵏偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼崅揷惣忛昦堾偺椣棟埾堳夛偐傜丆屄恖忣曬偺墈棗偼忋墇巗忣曬岞奐丒屄恖忣曬曐岇惂搙摍怰媍夛偐傜偦傟偧傟彸擣傪摼偨丏
- 亂寢壥亃懳徾幰悢偼H22擭1寧傑偱偵57柤偑巰朣丒揮弌偟嵟廔揑偵932柤偱偁傞丏偦偺偆偪516柤乮抝惈262柤丆彈惈254柤丆暯嬒擭楊81.1嵨乯偑堦師挷嵏傪廔椆偟371柤偑擇師挷嵏偺懳徾偲側偭偨丏偙偺偆偪234柤乮抝惈121柤丆彈惈113柤丆暯嬒擭楊83.4嵨乯偑堛巘偺恌嶡傪庴偗丆偦偺妋掕恌抐偺寢壥乮寉搙擣抦婡擻忈奞63柤丆傾儖僣僴僀儅乕宆擣抦徢68柤丆寣娗惈擣抦徢45柤丆儗價乕彫懱宆擣抦徢2柤乯偼慡崙桳昦棪挷嵏尋媶偵廤寁偝傟偨丏
丂杮尋媶偐傜尒偊偰偒偨偙偲偼嘆擣抦徢婡擻忈奞傪桳偡傞偑夘岇曐尟枹棙梡幰36柤嘇婛懚僒乕價僗埲奜偺場巕乮擾嶌嬈丆攝嬼幰丆抧堟偺巟偊偲尒庣傝側偳乯偺廳梫惈嘊愱栧堛恌嶡傛傝傕恎懱壢堛巘偺帯椕働傾偑庡偲側偭偰偄傞嘋擣抦徢偺朘栤働傾僯乕僘偼恎懱幘姵偵斾傋偰彮側偄丏
- 亂峫嶡亃杮尋媶偱柧傜偐偵側偭偨暯嬒擭楊80嵨埲忋偺擣抦徢挻崅楊幰偼恎懱婡擻偺掅壓傕敽偄丆抧堟働傾偺堊偵偼廫暘側夘岇曐尟棙梡壓偱忋墇巗偺懡條側抧堟摿惈傪専摙偟娭學彅婡娭偑楢実偟偨幙偺崅偄堛椕暉巸僒乕價僗採嫙偑昁梫偱偁傞丏
-
- 丂
丂
- 6寧16擔丂嫗墹僾儔僓儂僥儖杮娰43奒僗僞乕儔僀僩丂16:59乣17:51
- 恄宱怱棟嘆
- 嵗挿丗 惣愳丂棽乮戝嶃晎棫戝妛憤崌儕僴價儕僥乕僔儑儞妛晹乯
- P-A-13丂
- 寉搙擣抦忈奞偐傜傾儖僣僴僀儅乕宆擣抦徢傊偺恑峴梊應偵桳梡側恄宱怱棟妛揑専嵏偺専摙
- 壛摗丂桟壚乮嫗搒晎棫堛壢戝妛戝妛堾堛妛尋媶壢惛恄婡擻昦懺妛乯
- 亂栚揑亃Mild Cognitive Impairment乮MCI乯偺拞偱傕偲偔偵Alzheimer's Disease乮AD乯傊偺堏峴棪偑崅偄偲偝傟傞偺偑amnestic MCI乮aMCI乯偱偁傞丏偦偙偱丆杮尋媶偱偼暋悢偺恄宱怱棟妛揑専嵏傪梡偄丆aMCI偺専弌偵桳岠側巜昗丆媦傃aMCI偐傜AD傊偺堏峴傪梊應偡傞偺偵塻晀側巜昗傪専摙偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丏
- 亂曽朄亃懳徾偼Control孮24柤偲丆棔栰昦堾傕偺朰傟奜棃傪庴恌偟aMCI偲恌抐偝傟偨姵幰偺偆偪栺2擭娫偺捛愓挷嵏偑壜擻偱偁偭偨29柤偱偁傞丏aMCI29柤偺撪栿偼丆捛愓婜娫拞偵aMCI偺恌抐婎弨偵偲偳傑偭偨MCI/MCI孮12柤偲probable AD偺恌抐婎弨偵帄偭偨MCI/AD孮17柤偱偁傞丏曽朄偼丆懳徾幰慡堳偵MMSE丆ADAS乚cog丆CDT乮CLOX朄乯丆TMT傪屄暿偵巤峴偟丆MCI/MCI孮偲MCI/AD孮偵偼儕僶乕儈乕僪峴摦婰壇専嵏傕壛偊偰幚巤偟偨丏暘愅偼丆MCI/MCI孮偲MCI/AD孮偺2孮娫偵偍偗傞墫巁僪僱儁僕儖搳梌偲側偭偨徢椺悢偺斾棪偵偮偄偰冊2専掕傪峴偭偨丏傑偨丆aMCI偺拞偱傕擣抦婡擻偺掅壓偑婰壇偺傒偐暋悢椞堟偵搉傞偐偱偦偺屻偺AD傊偺恑揥偵嵎偑偁傞偐斲偐傪専摙偡傞偨傔丆aMCI single domain乮aMCIs乯偲aMCI multiple domain乮aMCIm乯偺斾棪偵偮偄偰傕冊2専掕傪峴偭偨丏師偄偱Control孮偲MCI/MCI孮丆MCI/MCI孮偲MCI/AD孮傪斾妑懳徾偲偟偰丆奺恄宱怱棟妛揑専嵏偺憤摼揰偲壓埵専嵏摼揰傪愢柧曄悢丆恌抐傪栚揑曄悢偲偟丆廳夞婣暘愅傪揔梡偟偰桳岠側愢柧曄悢傪僗僥僢僾儚僀僘朄偵傛傝慖戰偟偨丏側偍丆MCI/MCI孮偲MCI/AD孮偵偮偄偰偼丆偄偢傟傕弶恌帪偺恄宱怱棟妛揑専嵏偺惉愌傪暘愅偵梡偄偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼棔栰昦堾椣棟埾堳夛偺彸擣傪庴偗丆姵幰側偄偟壠懓偵偼尋媶偺庡巪偲拞抐偺帺桼丆媦傃摻柤惈偺妋曐側偳偵偮偄偰愢柧偺忋摨堄傪摼偨丏
- 亂寢壥亃冊2専掕偺寢壥丆MCI/MCI孮偲MCI/AD孮偺2孮娫偱捛愓婜娫拞偵墫巁僪僱儁僕儖搳梌偲側偭偨徢椺悢偼桳堄偵MCI/AD孮偱懡偐偭偨乮冊2乮1乯亖7.13丆p亙.01乯丏堦曽丆aMCIs偲aMCIm偺斾棪偵桳堄嵎偼傒傜傟側偐偭偨乮冊2乮1乯亖0.55丆ns乯丏傑偨丆Control孮偲MCI/MCI孮傪懳徾偵廳夞婣暘愅傪峴偭偨寢壥丆椉孮偺敾暿偵桳岠側巜昗偲偟偰ADAS乚cog偺扨岅嵞惗偲娤擮塣摦丆MMSE偺Serial 7's偲嵞惗丆ADAS乚cog峔惉峴堊丆TMT part B岆斀墳悢偑弴偵嵦戰偝傟丆婑梌棪偼81.7亾偱偁偭偨乮昞1乯丏MCI/MCI孮偲MCI/AD孮傪懳徾偲偟偨廳夞婣暘愅寢壥偱偼丆MMSE嵞惗丆儕僶乕儈乕僪峴摦婰壇専嵏丂摴弴乮抶墑乯偑弴偵嵦戰偝傟丆婑梌棪偼45.9亾偱偁偭偨乮昞2乯丏
- 亂峫嶡亃Control孮偲aMCI孮偺斾妑偱偼丆挳妎揑尵岅婰柫椡丆儚乕僉儞僌儊儌儕乕丆悑峴婡擻丆帇嬻娫擣抦峔惉擻椡側偳傪斀塮偡傞壽戣偑椉幰偺敾暿偵桳岠偱偁傝丆憤崌揑側擣抦婡擻傪昡壙偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞偲峫偊傜傟傞丏傑偨丆aMCI偺拞偱傕AD偵堏峴偡傞壜擻惈偑偁傞応崌丆aMCI偺帪揰偱扨岅傗摴弴偺抶墑嵞惗壽戣偺惉愌偑敾暿偵桳梡側偙偲偑帵偝傟丆愭峴尋媶偲傕堦抳偡傞寢壥偲側偭偨丏崱屻丆偝傜偵捛愓挷嵏傪宲懕偟偰峴偄丆寬忢偐傜aMCI丆AD傊偺堏峴傪傛傝惓妋偵梊應偱偒傞僥僗僩丒僶僢僥儕乕傪専摙偡傞偙偲偑壽戣偱偁傞丏
- P-A-14丂
- 奐嬈堛偵偍偗傞ADAS-J cog偺摫擖丟怴婯峈擣抦徢栻偺巊偄暘偗偵旛偊偰
- 暯堜丂栁晇乮擖娫暯堜僋儕僯僢僋乯
- 亂栚揑亃傛偆傗偔変偑崙偱傕暋悢偺峈擣抦徢栻偑巊偊傞傛偆偵側偭偨丏偙傟傜傪堦懱偳偆傗偭偰巊偄暘偗偨傜傛偄偺偩傠偆偐丠丂峈擣抦徢栻偺岠壥敾掕偺擄偟偝偼丆埲慜偐傜栤戣偵側偭偰偄偨丏尰悽戙偺峈擣抦徢栻偺懡偔偼丆偦偺奐敪偺庡梫僄儞僪億僀儞僩傪ADAS cog乮擔杮偱偼ADAS乚J cog乯偱應掕偟偰偄傞丏擣抦婡擻偺曄壔傪塻晀偵偲傜偊傞偙偲偑壜擻偱偁傞偲偺棟桼偱丆暷崙怘昳堛栻昳嬊乮FDA乯偑峈擣抦徢栻帯尡偵偍偗傞巊梡傪悇彠偟偨偨傔偱偁傞丏偙偺ADAS乚J cog偑丆僱僢僩儚乕僋僐儞僺儏乕僞乕傪梡偄傞偙偲偵傛傝丆奐嬈堛儗儀儖偱傕應掕壜擻偲側偭偨偺偱丆徯夘偡傞丏
- 亂曽朄亃應掕偺庤弴帺懱偼廬棃偺ADAS乚J cog偲摨堦側偺偱丆姰慡側僨乕僞偺屳姺惈偑妋曐偝傟偰偄傞丏巊梡偡傞僱僢僩儚乕僋僐儞僺儏乕僞乕偼僞僢僠僷僱儖曽幃偱丆梊旛抦幆偺彮側偄曽偱傕擖椡偑弌棃傞傛偆偵岺晇偝傟偰偄傞丏斚嶨偱偁偭偨嵦揰嶌嬈偑帺摦壔偝傟偨偙偲偵傛傝丆奐嬈堛儗儀儖偱偺塣梡偑廫暘偵壜擻偲側偭偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃乽堛椕婡娭偵偍偗傞屄恖忣曬偺曐岇乿乮暯惉17擭2寧丆擔杮堛巘夛乯偵弨嫆偟偨丏
- 亂寢壥亃墘幰偺巤愝偵偍偄偰丆偙傟傑偱偺偲偙傠偼丆庡娤揑偵婰壇忈奞傪慽偊傞偑丆捠忢偺HDS乚R側偳偱偼僇僢僩僆僼抣傪戝暆偵挻偊偰偟傑偆曽傪懳徾偵丆栺敿擭偺娫妘偱應掕偟丆昦揑儗儀儖偺恑峴惈婰壇忈奞偺桳柍傪妋擣偡傞宍偱塣梡偟偰偒偨丏
丂ADAS乚J cog偺尨斉偱偁傞ADAS cog偼丆傾儖僣僴僀儅乕昦偺傒側傜偢寬忢懳徠孮偺僨乕僞傕朙晉偵岞奐偝傟偰偄傞丏偦傟傜偲斾妑偟側偑傜丆専嵏寢壥傪杮恖丒壠懓偵愢柧偡傞偙偲偑丆斵傜偺晄埨傪寉尭偡傞偺偵桳岠偱偁傞偲姶偠傜傟偨丏
- 亂峫嶡亃崱屻偼丆峈擣抦徢栻偺搳梌奐巒帪偲24廡乮栺敿擭乯屻偵ADAS乚J cog傪應掕偟丆偦偺寢壥傪奺栻嵻偺帯尡榑暥偲捈愙斾妑偡傞梊掕偱偁傞丏
丂摉嬊偑怰嵏偺抜奒偱婜懸偟偨岠壥偑丆幚嵺偵敪尰偟偰偄傞偐偳偆偐偼丆杮恖丒壠懓偵偲偭偰丆旕忢偵愗幚側栤戣偱偁傞丏偦偺妋擣偑丆傛偆傗偔奐嬈堛儗儀儖偱丆偁傞掱搙傑偱弌棃傞傛偆偵側偭偨丏偙偆偟偨宱尡偲忣曬偺廤愊偑丆暋悢偺峈擣抦徢栻傪杮摉偵巊偄偙側偡偨傔偵丆昁梫偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丏
丂崱夞嫙棗偟偨僔僗僥儉偼丆僨乕僞傪僒乕僶乕偱堦妵娗棟偟偰偄傞丏墘幰偑帋梡偟偨僶乕僕儑儞偼ADAS乚J cog偺傒傪搵嵹偟偰偄偨偑丆偝傜偵HDS乚
R偲BEHAVE乚AD傪捛壛偟偨僶乕僕儑儞偑婛偵姰惉偟偰偄傞丏偙偆偟偨僔僗僥儉偑峀偔晛媦偟丆埨掕偟偨塣梡偑峴傢傟偨側傜偽丆乽偳偺栻偑丆偳偺僗僥乕僕偺擣抦徢偵丆偳偺傛偆偵岠偄偰偄傞偐乿偑丆彮側偔偲傕尰嵼傛傝惓妋偵丆攃埇壜擻偲側傞偱偁傠偆丏BPSD傗ADL偺忣曬傕暲峴偟偰廤愊偟丆偦傟傜傪杮恖丒壠懓偺尰忬偵懄偟偰拪弌偟丆斵傜帺恎偵棟夝壜擻側宍偱採嫙偱偒傞傛偆偵側傟偽丆擣抦徢偵懳偟偰乽幚懺埲忋偺嫲晐乿傪書偐偢偵嵪傒丆傛傝愊嬌揑側恖惗愝寁偑壜擻偲側傞偺偱偼側偄偐丏
- P-A-15丂
- 桳堄側婰壇忈奞傪帵偝側偄憗婜amnestic MCI丟暔朰傟僪僢僋偵傛傞専弌
- 懞嶳丂寷抝乮杒棦戝妛堛椕塹惗妛晹丆弴揤摪搶嫗峕搶崅楊幰堛椕僙儞僞乕乯
- 亂栚揑亃婰壇忈奞傪庡懱偲偡傞寉搙擣抦忈奞乮amnestic mild cognitive impairment;aMCI乯偺恌抐偵偼丆媞娤揑偵應掕偝傟偨婰壇婡擻偺桳堄側掅壓偑昁梫偱偁傞丏偙傟傑偱偺懡偔偺尋媶偱偼丆摼揰偑摨偠擭楊孮偺暯嬒傛傝傕1.0SD側偄偟1.5SD埲壓偱偁偭偨懳徾幰傪aMCI偲偟偰偄傞丏偟偐偟丆擭楊憡墳偐傜aMCI傑偱偺夁掱偼慟恑揑丒楢懕揑偱偁傝丆偙傟傪婎弨偵偡傞偲憗婜偺aMCI偼専弌偝傟側偄応崌偑偁傞丏杮尋媶偱偼丆暔朰傟僪僢僋偱専弌偝傟偨憗婜偺帠椺傪懳徾偵丆aMCI偺憗婜敪尒偵偮偄偰専摙偟偨丏
- 亂曽朄亃弴揤摪搶嫗峕搶崅楊幰堛椕僙儞僞乕偺暔朰傟僪僢僋傪庴恌偟偨寢壥丆aMCI偺恌抐婎弨偼枮偨偝側偄傕偺偺丆憗婜偺aMCI偑媈傢傟偨8柤傪Early MCI孮乮E孮乯丆揟宆揑側aMCI偲恌抐偝傟E孮偲擭楊丒嫵堢擭悢偑摨掱搙偺10柤傪MCI孮乮M孮乯偲偟偨丏傑偨丆擭楊丒嫵堢擭悢偑摨掱搙偱丆MCI傪娷傔惛恄丒恄宱幘姵偑擣傔傜傟側偄崅楊幰6柤傪Normal孮乮N孮乯偲偟偨丏
丂偙偺暔朰傟僪僢僋偱偼丆惛恄恄宱妛揑恌嶡偺傎偐丆専嵏偲偟偰摢晹MRI傗擼18F乚FDG PET丆徻嵶側恄宱怱棟専嵏傪峴側偭偰偄傞丏杮尋媶偱偼丆偙傟傜偺専嵏寢壥傪3孮娫偱斾妑偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼摉僙儞僞乕偺椣棟埾堳夛偺彸擣傪庴偗偨尋媶偺堦晹偱偁傝丆懳徾幰偵偼彂柺偵傛傞尋媶嫤椡偺摨堄傪摼偨丏
- 亂寢壥亃摢晹MRI偱偼丆N孮偼擭楊憡墳偺擼堔弅偑丆M孮偼奀攏椞堟傪拞怱偲偟偨寉搙偺擼堔弅偑擣傔傜傟偨丏E孮偺擼堔弅偼帠椺偵傛傝堎側偭偨偑丆慡懱揑偵偼擭楊憡墳偐傜偛偔寉搙偵傒傜傟傞掱搙偱偁偭偨丏擼18F乚FDG PET偱偼丆E孮偼屻晹懷忬夞傗懁摢摢捀楢崌栰偺堦晹偵桳堄側摐戙幱掅壓偑傒傜傟丆M孮偼掅壓偺掱搙偑嫮偔斖埻傕峀偐偭偨丏
丂恄宱怱棟専嵏偱偼丆N孮丆E孮丆M孮偺MMSE摼揰偼丆偦傟偧傟丆29.2亇1.6丆28.6亇1.5丆26.4亇1.6偱偁偭偨丏傑偨丆WMS乚R偺堦斒揑婰壇偼丆偦傟偧傟丆109.2亇12.9丆103.4亇8.1丆77.5亇10.1偱偁偭偨丏暘嶶暘愅偍傛傃懡廳斾妑偺寢壥丆椉専嵏偲傕N孮偲E孮偵偼桳堄嵎偼側偔丆M孮偼椉孮傛傝傕桳堄偵掅摼揰偩偭偨乮p亙.05乯丏堦曽丆WAIS乚嘨偺慡専嵏IQ偼丆偦傟偧傟丆112.2亇10.5丆126.5亇7.1丆111.4亇10.5偱偁偭偨丏暘嶶暘愅偍傛傃懡廳斾妑偺寢壥丆N孮偲M孮偵偼桳堄嵎偼側偔丆E孮偼椉孮傛傝傕桳堄偵崅摼揰偱偁偭偨乮p亙.05乯丏
- 亂峫嶡亃婰壇婡擻偺掅壓傪昡壙偡傞偨傔偵偼丆杮棃丆昦慜偺婡擻偑昡壙偝傟偰偄傞昁梫偑偁傞丏偟偐偟丆椪彴揑偵偼丆偦偺傛偆偵昦慜偺婡擻偑昡壙偝傟偰偄傞椺偼婬偱偁傝丆廲抐揑昡壙偼崲擄側応崌偑懡偄丏
丂杮尋媶偱偼丆N孮偲E孮偺WMS乚R摼揰偼摨掱搙偱偁偭偨偑丆WAIS乚嘨摼揰偼E孮偑懠孮傛傝傕崅偐偭偨丏偮傑傝E孮偼丆婰壇傪娷傔昦慜偺擣抦婡擻偑懠孮傛傝傕崅偐偭偨壜擻惈偑偁傞丏婰壇婡擻偲偦傟埲奜偺擣抦婡擻傪斾妑偡傞偙偲偱丆擭楊憡墳偺婰壇婡擻傪帵偡傛偆側憗婜偺aMCI偱傕専弌偱偒傞壜擻惈偑帵嵈偝傟偨丏傑偨丆憗婜偺aMCI傪懳徾偵偟偨怱棟嵏掕偱偼丆婰壇忈奞偲婰壇掅壓偼揑妋偵巊偄暘偗傞昁梫惈偑偁傞偲峫偊傜傟偨丏
丂偝傜偵擼18F乚FDG PET偱偼丆E孮偺傛偆側憗婜偺aMCI偱傕屻晹懷忬夞傗懁摢摢捀楢崌栰偵桳堄側摐戙幱掅壓偑傒傜傟丆偙偺専嵏偺桳梡惈傕帵嵈偝傟偨丏
- P-A-16丂
- Addenbrooke乫s Cognitive Examination Revised乮ACE-R乯擔杮岅斉偺嶌惉
- 媑揷丂塸摑乮撿壀嶳堛椕僙儞僞乕恄宱撪壢丆壀嶳戝妛戝妛堾堛帟栻妛憤崌尋媶壢惛恄恄宱昦懺妛乯
- 亂栚揑亃擣抦徢偺擔忢恌椕偵偍偄偰偼丆娙曋偵巤峴偱偒丆偟偐傕寉搙偺擣抦婡擻掅壓偵懳偟偰姶搙丆摿堎搙偺崅偄擣抦婡擻昡壙朄偑媮傔傜傟偰偄傞丏崱夞変乆偼Addenbrooke's Cognitive Examination Revised乮ACE乚R, Mioshi et al. 2006乯偺擔杮岅斉傪嶌惉偟丆偦偺怣棅惈丒懨摉惈偺専摙丆偍傛傃寉搙擣抦忈奞偲擣抦徢偺専弌偵偍偗傞姶搙丆摿堎搙偺専徹傪峴偭偨丏
- 亂曽朄亃ACE乚R偼拲堄乛尒摉幆乮18揰乯丆婰壇乮26揰乯丆棳挩惈乮14揰乯丆尵岅乮26揰乯丆帇嬻娫擣抦乮16揰乯偺5偮偺壓埵崁栚偐傜側傞擣抦婡擻専嵏偱偁傞乮憤摼揰100揰乯丏擔杮岅斉嶌惉偵偁偨偭偰偼擔杮恖崅楊幰偵揔墳偡傞傛偆偵堦晹傪夵曄偟偨丏壀嶳戝妛昦堾惛恄恄宱壢傕偺朰傟奜棃傪庴恌偟偨擣抦徢姵幰130柤乮傾儖僣僴僀儅乕宆擣抦徢106柤丆寣娗忈奞傪敽偆傾儖僣僴僀儅乕宆擣抦徢7柤丆寣娗惈擣抦徢3柤丆慜摢懁摢宆擣抦徢8柤丆儗價乕彫懱宆擣抦徢6柤乯偲寉搙擣抦忈奞乮MCI乯39柤丆偍傛傃惓忢崅楊幰73柤傪懳徾偲偟偰丆擣抦徢偺恌抐丒昡壙偵昁梫側専嵏偵壛偊擔杮岅斉ACE乚R傪巤峴偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃専嵏偺幚巤偵偁偨偭偰専嵏僨乕僞偺尋媶棙梡偵娭偡傞杮恖偍傛傃壠懓偺摨堄傪摼偨丏傑偨屄恖忣曬曐岇偵攝椂偟偨丏
- 亂寢壥亃ROC夝愅偵傕偲偯偔ACE乚R偺帄揔僇僢僩僆僼抣偼丆MCI孮乛惓忢孮偱88乛89揰乮姶搙0.87丆摿堎搙0.92乯丆擣抦徢孮乛惓忢孮偱82乛83揰乮姶搙0.99丆摿堎搙0.99乯偱偁偭偨丏摨帪偵巤峴偟偨MMSE偲斾妑偡傞偲丆MCI偺専弌偵偍偄偰偼ACE乚R偺曽偑桪傟偰偄偨乮ROC嬋慄壓柺愊偑ACE乚R偼0.952丆MMSE偼0.868偱桳堄嵎偁傝乯偑丆擣抦徢偺専弌偵偍偄偰偼嵎偑側偐偭偨乮ROC嬋慄壓柺愊偑ACE乚R偼0.999丆MMSE偼0.993乯丏専嵏幰娫怣棅惈乮ICC亖0.999乯丆嵞帋尡怣棅惈乮ICC亖0.883乯偍傛傃撪揑惍崌惈乮Cronbach's alpha亖0.903乯偼椙岲偱偁偭偨丏ACE乚R憤摼揰偲Clinical Dementia Rating乮CDR乯摼揰偍傛傃CDR sum of boxes摼揰偼崅偄憡娭乮Spearman's rho亖亅0.851偍傛傃亖亅0.895乯傪帵偟偨丏
- 亂峫嶡亃擔杮岅斉ACE乚R偼怣棅惈丆懨摉惈偲傕偵崅偔丆寉搙擣抦忈奞偍傛傃擣抦徢傪惓妋偵専弌偡傞偙偲偑偱偒偨丏ACE乚R偼斾妑揑娙曋側僥僗僩偺偨傔15乣20暘偱巤峴丒嵦揰偑壜擻偱偁傝丆擔忢恌椕偱偺僗僋儕乕僯儞僌専嵏偲偟偰巊梡壜擻偲巚傢傟傞丏側偍擔杮岅斉ACE乚R偺僥僗僩梡巻偍傛傃巤峴丒嵦揰偺庤堷偒偼丆尨挊幰偺僂僃僽僒僀僩亙http://www.ftdrg.org/亜偐傜擖庤偱偒傞丏
- P-A-17丂
- Agitation Behavior in Dementia Scale (ABID)偺昗弨壔偺専摙
- 捁堜丂彑媊乮柤屆壆巗棫戝妛戝妛堾堛妛尋媶壢惛恄丒擣抦丒峴摦堛妛丆敧帠昦堾乯
- 亂栚揑亃擣抦徢偺徟憞丒峌寕惈偼丆姵幰帺恎偲夘岇幰偺QOL偵塭嬁傪梌偊傞丏偦偺偨傔丆擣抦徢偺徟憞丒峌寕惈傗夘岇幰偺晧扴傪惓妋偵昡壙偡傞偙偲偼揔愗側帯椕傗働傾傪偡傞忋偱昁梫晄壜寚偱偁傞丏偟偐偟杮朚偱偼丆擣抦徢偺徟憞丒峌寕惈偲夘岇晧扴傪摨帪偵昡壙偡傞昗弨壔偝傟偨広搙偼傑偩峫埬偝傟偰偄側偄丏偦偙偱変乆偼Logsdon傜偵傛傝憂埬偝傟偨擣抦徢偺徟憞傗峌寕惈偺昡壙広搙偱偁傞Agitation Behavior in Dementia Scale乮ABID乯偺擔杮岅斉偺怣棅惈偲懨摉惈傪専摙偟偨丏
- 亂曽朄亃柤屆壆巗棫戝妛偙偙傠偺堛椕僙儞僞乕奜棃傪2003擭9寧偐傜2004擭8寧傑偱偵庴恌偟偨傾儖僣僴僀儅乕昦偺姵幰149柤傪懳徾偲偟偨丏姵幰偲夘岇幰偺攚宨忣曬傪廂廤偟丆懳徾幰偵Mini mental state examination乮MMSE乯傪峴偄丆庡夘岇幰偵懳偟偰偼擔杮岅斉Agitation Behavior in Dementia Scale乮ABID乯偺昡壙偵壛偊丆Cohen乚Mansfield Agitation Inventory乮CMAI乯偲Zarit Caregiver Burden Interview乮ZBI乯傕巤峴偟偨丏
丂撪揑怣棅惈偺専摙偺偨傔偵丆Cronbach's alpha coefficient傪寁嶼偟丆奜揑怣棅惈偼丆70柤偵懳偟偰test乚retest乮1儢寧屻偺嵞巤峴乯傪ANOVA乚ICC偱昡壙偟偨丏暲懚懨摉惈偺昡壙偲偟偰丆ABID偺昿搙偺崁栚偲CMAI偲偺憡娭傪丆ABID偺夘岇幰偺斀墳偲ZBI偲偺憡娭傪媮傔偨丏偝傜偵峔惉奣擮懨摉惈偺妋擣偺偨傔丆ABID偺昿搙偺奺崁栚傪僶儕儅僢僋僗夞揮偟偰場巕暘愅傪偍偙側偭偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃偙偺尋媶偼丆柤屆壆巗棫戝妛堛妛晹椣棟埾堳夛偵偍偄偰彸擣傪摼偰丆偡傋偰偺懳徾幰偵栚揑偲曽朄傪愢柧偟偨偆偊偱摨堄傪摼偰偄傞丏
- 亂寢壥亃擔杮岅斉ABID偺昿搙昡壙偺Cronbach's 兛亖0.89偍傛傃斀墳昡壙偺Cronbach's 兛亖0.92偱偁傝桪傟偨撪揑怣棅惈傪帵偟偨丏test乚retest偱傕ABID偺昿搙昡壙乮ANOVA ICC亖0.85乯偲斀墳昡壙乮ANOVA ICC亖0.89乯偲傕偵桪傟偨奜揑怣棅惈傪帵偟偨丏ABID偺昿搙昡壙偲CMAI偼桳堄側憡娭偑偁傝丆ABID偺斀墳昡壙偲ZBI偲傕桳堄側憡娭傪帵偟丆懨摉惈偼椙岲偱偁偭偨丏壛偊偰丆場巕暘愅偼丆恎懱揑側徟憞姶偺偁傞峴摦丆尵岅揑側徟憞姶偺偁傞峴摦丆惛恄徢忬偺3場巕偐傜峔惉偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丏
- 亂峫嶡亃擔杮岅斉ABID偺怣棅惈偲懨摉惈偼椙岲偱偁傝丆杮朚偱傕偙偺広搙偺巊梡偼壜擻偱偁傞丏
丂傾儖僣僴僀儅乕昦偺徟憞姶偺3場巕偵傛傞峔惉傕柧傜偐偵側偭偨丏崱屻丆椪彴揑夘擖偺傾僂僩僇儉偺應掕偲偟偰桳梡側広搙偺傂偲偮偲側傞偲巚傢傟傞丏
- P-A-18丂
- 傾儖僣僴僀儅乕昦姵幰偵擣傔傜傟傞嫽暠偺恄宱婎斦偺専摙
- 栰懞丂宑巕乮戝嶃戝妛戝妛堾堛妛宯尋媶壢惛恄堛妛嫵幒乯
- 亂栚揑亃傾儖僣僴僀儅乕昦乮AD乯姵幰偵擣傔傜傟傞嫽暠傪暘椶偟丆偦傟偧傟偵懳墳偡傞恄宱婎斦偺専摙傪偡傞丏
- 亂曽朄亃懳徾偼丆2004擭1寧偐傜2009擭2寧偺娫偵戝嶃戝妛堛妛晹晬懏昦堾恄宱壢惛恄壢恄宱怱棟奜棃傪庴恌偟偨姵幰偱丆NINCDS乚ADRDA偺probable AD偺恌抐婎弨傪枮偨偟丆弶恌帪60嵨埲忋丆怣棅偺偍偗傞庡夘岇幰偐傜挳庢偟偨Neuropsychiatric Inventory乮NPI乯偱嫽暠偑擣傔傜傟丆123I乚IMP SPECT偑巤峴偝傟偰偄傞36椺乮暯嬒擭楊亖75.1亇6.4丆抝惈丗彈惈亖11丗25丆MMSE暯嬒摼揰亖19.0亇5.0乯丏NPI嫽暠偺7偮偺壓埵幙栤乮夘岇傊偺嫅斲丆婃屌丆旕嫤椡揑丆埖偄偵偔偄懺搙丆嫨傇丒埆懺傪偮偔丆暔偵偁偨傞丆恖傪彎偮偗傞乯偵偮偄偰丆偁傝丒側偟乮1丒0乯偱昡壙偟偨丏壓埵幙栤偺偆偪丆5椺埲忋偱擣傔傜傟偨傕偺偵偮偄偰場巕暘愅傪峴偭偨丏奺娤應曄悢偵偮偄偰場巕晧壸検偑0.5埲忋偺傕偺傪桳堄偲敾掕偟偨丏奺場巕偵偮偄偰嶼弌偝傟傞場巕摼揰偲擼寣棳曄壔偲偺娭楢傪専摙偡傞偨傔丆SPM5傪梡偄丆姵幰偺擭楊丆MMSE偺摼揰傪嫟曄検偵擖傟丆廳夞婣暘愅傪峴偭偨乮uncorrected p亙0.01乯丏
- 亂椣棟揑攝椂亃摼傜傟偨屄恖忣曬偼慡偰摻柤壔偟丆屄恖偑摿掕偝傟側偄傛偆偵攝椂偟偨丏
- 亂寢壥亃懳徾偺NPI嫽暠偺暯嬒摼揰乮昿搙偲廳徢搙偺愊乯偼丆3.6亇2.4偱偁偭偨丏傕偭偲傕懡偔擣傔傜傟偨偺偼丆婃屌乮27椺乯偱丆嫨傇丒埆懺傪偮偔乮20椺乯丆旕嫤椡揑乮15椺乯丆夘岇傊偺嫅斲乮13椺乯丆暔偵偁偨傞乮13椺乯丆埖偄偵偔偄懺搙乮3椺乯丆恖傪彎偮偗傞乮3椺乯偲懕偄偨丏5椺埲忋偱擣傔傜傟偨5偮偺壓埵幙栤偵偮偄偰場巕暘愅傪峴偭偨寢壥丆2偮偺場巕偵暘椶偝傟偨丏場巕1偵暘椶偝傟偨偺偼旕嫤椡揑丆夘岇傊偺嫅斲丆婃屌偱丆偦傟偧傟偺場巕晧壸検偼0.823丆0.774丆0.606偱偁偭偨丏場巕2偵暘椶偝傟偨偺偼嫨傇丒埆懺傪偮偔丆暔偵偁偨傞偱丆偦傟偧傟偺場巕晧壸検偼0.744偲0.643偱偁偭偨丏場巕1偲惓偺憡娭傪帵偟偨擼寣棳曄壔晹埵偼嵍忋慜摢椞堟撪懁丆嵍壓摢捀彫梩丆嵍壓慜摢夞奜懁偱偁偭偨丏場巕1偲晧偺憡娭傪帵偟偨擼寣棳曄壔晹埵偼椉懁旜忬妀廃曈丆塃搰偱偁偭偨丏場巕2偲惓偺憡娭傪帵偟偨擼寣棳曄壔晹埵偼攚懁屻懷忬旂幙偲嵍懁摢乗摢捀乗屻摢椞堟偱偁偭偨丏場巕2偲晧偺憡娭傪帵偟偨擼寣棳曄壔晹埵偼椉懁慜摢梩撪懁丆椉懁慜摢梩娽鈢柺椞堟丆椉懁懁摢乗摢捀椞堟偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃AD偺嫽暠偼2場巕偵暘椶偱偒偨丏場巕1偼旕嫤椡揑丆夘岇傊偺嫅斲丆婃屌偑暘椶偝傟丆乽掞峈乿偲峫偊傜傟偨丏場巕1偵娭楢偡傞恄宱婎斦偼嵍慜摢椞堟撪懁偺憡懳揑槾恑偲椉懁旜忬妀丆塃搰偺掅壓偱偁偭偨丏敪摦惈偑槾恑偟丆曬廣宯傗僼傿乕僪僶僢僋婡峔偺攋抅偵傛傝丆懳恖娭學偵巟忈傪偒偨偡拞偱丆掞峈偑昞弌偝傟傞偲峫偊傜傟偨丏場巕2偼嫨傇丒埆懺傪偮偔丆暔偵偁偨傞偑暘椶偝傟丆乽朶椡乿偲峫偊傜傟偨丏場巕2偵娭楢偡傞恄宱婎斦偼攚懁屻晹懷忬旂幙偺憡懳揑槾恑偲椉懁慜摢梩撪懁偲慜摢梩娽鈢椞堟偺掅壓偱偁偭偨丏忣摦婡擻偺槾恑偱娐嫬傗恖娫娭學側偳偵晀姶偵側傞堦曽丆峴摦偺梷惂偑崲擄偵側傞偙偲偑朶椡峴堊偵宷偑傞偲峫偊傜傟偨丏
-
- 丂
丂
- 6寧16擔丂嫗墹僾儔僓儂僥儖杮娰43奒僗僞乕儔僀僩丂13:45乣14:30
- 塽妛巤愝嘆
- 嵗挿丗 拞搱丂媊暥乮嶰堜婰擮昦堾乯
- P-B-1丂
- 擣抦徢愱栧奜棃傪庴恌偡傞姵幰偺弶恌帪摨嫃幰丒摨敽幰偵娭偡傞専摙丟搒怱晹偲抧曽搒巗偵偍偗傞壠懓夘岇婎斦偺抧堟斾妑
- 昳愳丂弐堦榊乮搶嫗帨宐夛堛壢戝妛惛恄堛妛島嵗乯
- 亂攚宨亃擣抦徢愱栧奜棃偑奺抧偱奐愝偝傟丆憗婜恌抐丒憗婜帯椕偵娭偡傞孾敪傕恑傒丆庴恌姵幰悢傕憹偊丆寉搙擣抦忈奞悈弨傪娷傔偨條乆側懳徾偑庴恌偡傞傛偆偵側偭偨丏擣抦徢偺恌抐偵偍偄偰偼峴摦娤嶡偵傛傞惗妶忬嫷偺攃埇偑廳梫偱偁傝丆帯椕傗働傾偵偍偄偰傕壠懓夘岇幰傪拞怱偲偟偨僉乕僷乕僜儞偺嫤椡偑晄壜寚偩偑丆壠懓峔憿偺曄壔偐傜丆愱栧奜棃偵扨恎偱庴恌偡傞崅楊幰傕憹壛偟偰偄傞丏偙偺傛偆側擣抦徢姵幰傪庢傝姫偔壠懓夘岇婎斦偺幚懺偼戝搒巗寳偲抧曽搒巗偱偼堎側傞偲峫偊傜傟傞丏
- 亂栚揑亃搒怱晹偲抧曽搒巗偺戝妛晬懏昦堾擣抦徢愱栧奜棃傪庴恌偡傞擣抦徢姵幰偺嫃廧宍懺丆弶恌帪摨嫃幰丒摨敽幰傪挷傋傞偙偲偱丆壠懓夘岇婎斦偵娭偡傞尰忬攃埇偲抧堟嵎斾妑傪峴偆丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮専摙偼尋媶嶲壛偺摨堄傪摼偨楢懕椺傪懳徾偲偟偰偄傞丏摻柤惈偺曐帩媦傃屄恖忣曬偺棳弌偵偼廫暘偵攝椂偟偨丏
- 亂曽朄亃2008擭4寧偐傜2009擭3寧傑偱偵搶嫗帨宐夛堛壢戝妛晬懏昦堾惛恄恄宱壢乮搒怱晹乯偍傛傃孎杮戝妛堛妛晹晬懏昦堾恄宱惛恄壢乮抧曽搒巗乯偺擣抦徢愱栧奜棃傪庴恌偟偨姵幰楢懕椺傪懳徾偲偟偨丏搒怱晹偱偼丆婜娫拞憤庴恌幰142椺偺偆偪擣抦徢姵幰偼99椺偱偁傝丆抧曽搒巗偱偼憤庴恌幰260椺偺偆偪丆擣抦徢姵幰偼172椺偱偁偭偨丏懳徾偺弶恌帪擭楊丆惈暿丆椪彴恌抐丆滊昦婜娫丆嫵堢擭悢丆MMSE摼揰丆CDR廳徢搙丆嫃廧宍懺丆弶恌帪摨嫃幰丆弶恌帪摨敽幰傪憃曽偺巤愝偱斾妑偟偨丏
- 亂寢壥亃擇孮娫偺惈暿丆弶恌帪擭楊丆滊昦婜娫丆CDR廳徢搙偱桳堄嵎偼擣傔側偐偭偨偑丆搒怱晹姵幰孮偱偼抧曽搒巗姵幰孮偵斾傋偰嫵堢擭悢偲MMSE僗僐傾偑桳堄偵崅偐偭偨丏傑偨丆搒怱晹姵幰孮偱偼抧曽搒巗姵幰孮傛傝傾儖僣僴僀儅乕昦偑懡偔娷傑傟偰偄偨乮69亾 vs 55亾乯丏嫃廧宍懺乮嵼戭乛巤愝擖強乯偼擇孮娫偱桳堄嵎偼擣傔側偐偭偨偑丆嫃廧宍懺乮嵼戭乛巤愝擖強乯偼擇孮娫偱桳堄嵎傪擣傔側偐偭偨丏嫃廧宍懺乮嵼戭乛巤愝擖強乯偼擇孮娫偱桳堄嵎傪擣傔側偐偭偨丏搒怱晹姵幰孮偺摨嫃幰偼丆攝嬼幰偺傒乮34亾乯偑嵟傕懡偔丆師偄偱撈嫃乮22亾乯丆巕嫙偺傒乮13亾乯偑懡偐偭偨偺偵懳偟丆抧曽搒巗姵幰孮偱偼攝嬼幰偺傒乮39亾乯丆攝嬼幰媦傃巕嫙悽懷乮23亾乯丆撈嫃乮14亾乯偺弴偵懡偐偭偨丏弶恌帪偺摨敽幰偼丆搒怱晹姵幰孮偵偍偄偰攝嬼幰埲奜偺壠懓乮49亾乯丆攝嬼幰乮27亾乯丆扨恎乮7亾乯偺弴偵懡偐偭偨偺偵懳偟丆抧曽搒巗姵幰孮偱偼攝嬼幰埲奜偺壠懓乮40亾乯丆攝嬼幰乮35亾乯偵師偄偱丆攝嬼幰偍傛傃懠偺壠懓乮18亾乯偑懡偔丆扨撈庴恌偼婬乮1亾乯偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃搒怱晹偺擣抦徢姵幰偼丆抧曽搒巗偲斾妑偟偰撈嫃傗扨撈庴恌椺偑懡偔丆壠懓悢柤偱庴恌偡傞椺偑彮側偐偭偨丏抧堟偵傛偭偰夘岇婎斦偑堎側傞偙偲傪帵嵈偟丆戝搒巗寳偱偼庡夘岇幰偲側傝摼傞僉乕僷乕僜儞偺慖掕偑崲擄側忬嫷偑憐掕偝傟偨丏壠懓夘岇幰偺晄嵼傗夘岇幰偺屒棫偼丆憗婜偺嵼戭夘岇攋抅偵偮側偑傞偨傔丆戝搒巗寳偺擣抦徢恌椕偵偍偄偰偼僉乕僷乕僜儞偺慖掕偵摿偵棷堄偡傞昁梫偑偁傞偲峫偊傜傟偨丏
- P-B-2丂
- 擣抦徢姵幰偺堓釕憿愝偵懳偡傞屻曽帇揑専摙
- 孎扟丂椇乮弴揤摪戝妛堛妛晹晬懏弴揤摪搶嫗峕搶崅楊幰堛椕僙儞僞乕乯
- 亂栚揑亃1980擭偵宱旂撪帇嬀揑堓釕憿愝弍乮PEG乯偑曬崘偝傟丆埲棃堓釕偺憿愝偼娙曋側弍幃偲偟偰晛媦偡傞傛偆偵側偭偨丏杮朚偱偼崅楊壔傗嵼戭夘岇偺摫擖傕偁傝丆墷暷偵斾傋崅楊幰傊偺巤峴偑懡偔側偭偰偄傞丏偦偺堦曽丆嬤擭擣抦徢姵幰偵懳偡傞堓釕憿愝傪尒捈偡傋偒偲偄偆堄尒偑擣傔傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丏崱夞変乆偼擣抦徢姵幰偵懳偡傞堓釕憿愝偺尰忬傪妋擣偡傞偨傔丆2002擭6寧偺奐堾偐傜2010擭12寧傑偱傪挷嵏婜娫偲偟丆婜娫拞偵摉堾偱PEG偑峴傢傟偨177柤偺姵幰偺偆偪丆擣抦徢姵幰151柤傪懳徾偵屻曽帇揑専摙傪峴偭偨丏
- 亂曽朄亃PEG偑峴傢傟偨擣抦徢姵幰偺惈嵎丒擭楊丒惛恄壢揑恌抐柤丒憿愝棟桼丒擖堾尦丒戅堾愭丒惗懚棪偵偮偄偰挷嵏偟偨丏傑偨妋擣偱偒偨徢椺偵偮偄偰偼丆弍慜偍傛傃6儢寧屻偺傾儖僽儈儞抣丒岆殝惈攛墛偺桳柍傪斾妑偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偼摉堾椣棟埾堳夛偵偍偗傞屻曽帇揑尋媶偺婎杮曽恓偵廬偭偰峴傢傟偨丏傑偨丆屄恖偺摿掕偑偱偒側偄傛偆昞婰摍偵懳偟攝椂偟偨丏
- 亂寢壥亃暯嬒擭楊偼79.1嵨丆抝惈丗彈惈亖85丗66偩偭偨丏恌抐柤偼AD偑50柤乮33.1亾乯丆VD偑59柤乮39.1亾乯丆AD偲VD偺崿崌宆擣抦徢偑7柤乮4.6亾乯丆FTD偑2柤乮1.3亾乯丆PDD丒DLB偑18柤乮11.9亾乯丆PSP偑7柤乮4.6亾乯丆CBD偑2柤乮1.3亾乯丆偦偺懠偑6柤乮4.0亾乯偩偭偨丏憿愝棟桼偼殝壓忈奞偑125柤乮82.8亾乯丆怘帠検掅壓偑24柤乮15.9亾乯丆捠夁忈奞丒奐岥忈奞偑偦傟偧傟1柤乮0.7亾乯偩偭偨丏擖堾尦偼帺戭偑80柤乮53.0亾乯丆榁寬偑11柤乮7.3亾乯丆桳椏榁恖儂乕儉偑13柤乮8.6亾乯丆摿梴偑21柤乮13.9亾乯丆懠昦堾偑24柤乮15.9亾乯丆偦偺懠2柤乮1.3亾乯偩偭偨偺偵懳偟丆戅堾愭偼帺戭偑32柤乮21.2亾乯丆榁寬偑4柤乮2.6亾乯丆儂乕儉偑16柤乮10.6亾乯丆摿梴偑20柤乮13.2亾乯丆懠昦堾偑51柤乮33.8亾乯丆巰朣偑26柤乮17.2亾乯丆偦偺懠2柤乮1.3亾乯偩偭偨丏惗懚棪偼1擭椵愊惗懚棪偑72.3亾丆2擭椵愊惗懚棪偑65.7亾丆3擭椵愊惗懚棪偑56.7亾偩偭偨丏弍慜偍傛傃6儢寧屻偺傾儖僽儈儞抣偑妋擣偱偒偨徢椺偼38柤偱丆暯嬒抣偼弍慜丒6儢寧屻偲傕2.9g/dl偱偁偭偨丏岆殝惈攛墛偺桳柍傪妋擣偱偒偨徢椺偼96柤偱丆弍慜偵岆殝惈攛墛傪崌暪偟偰偄偨64柤偺偆偪丆33柤偑弍屻6儢寧傑偱偵岆殝惈攛墛傪嵞敪偟偰偄偨丏堦曽丆弍慜偵岆殝惈攛墛傪崌暪偟偰偄側偐偭偨32柤偱偼丆弍屻6儢寧傑偱偵岆殝惈攛墛傪敪徢偟偨姵幰偼3柤偱偁偭偨丏
- 亂峫嶡亃擣抦徢姵幰偺恌抐柤偼AD偲VD偑懡偔傪愯傔偰偄偨丏PEG偺晛媦偵偼嵼戭堛椕偺悇恑傕娭學偟偰偄傞偑丆帺戭傊偺戅堾偼巤愝擖強丒揮堾傪壓夞偭偰偄偨丏弍慜丒弍屻偺傾儖僽儈儞抣偐傜偼丆擣抦徢姵幰傊偺堓釕憿愝偼塰梴忬懺偺堐帩偵偼桳岠偩偑丆戝暆側夵慞偼尒崬傔側偄偙偲偑擿傢傟偨丏傑偨岆殝偺桿敪場巕偵偼側傜側偄偑丆婛偵殝壓婡擻偵栤戣傪惗偠偰偄傞姵幰偵懳偟偰偼丆岆殝惈攛墛偺梊杊岠壥偼敄偄偲巚傢傟偨丏
丂摉擔偼摨婜娫偵宱旲宱娗塰梴偑峴傢傟偨擣抦徢姵幰孮偵偮偄偰偺挷嵏寢壥偵偮偄偰傕弎傋丆斾妑専摙偡傞丏
- P-B-3丂
- 愱栧昦堾偵擖堾偵帄傞BPSD偺慜岦偒懡巤愝嫟摨挷嵏
- 悪嶳丂攷捠乮戝嶃戝妛戝妛堾堛妛宯尋媶壢惛恄堛妛嫵幒乯
- 亂栚揑亃姵幰偑擖堾偵帄傞BPSD偲偦偺掱搙傪柧傜偐偵偡傞丏
- 亂曽朄亃懳徾偼丆愺崄嶳昦堾丆戝嶃戝妛堛妛晹晬懏昦堾恄宱壢丒惛恄壢丆偨傔側偑壏愹昦堾丆搶壛屆愳昦堾偵丆BPSD帯椕栚揑偱擖堾偟偨楢懕椺丏挷嵏婜娫偼偦傟偧傟偺昦堾偛偲偵堎側傞偑丆慡懱偱偼2009擭5寧11擔偐傜2010擭11寧30擔丏擖堾帪偵壠懓偵懳偟NPI傪巤峴偟偨丏摨帪偵堛巘偼丆NPI12崁栚偺偆偪丆偳偺崁栚偵傛傝姵幰偑擖堾偵帄偭偨偐慖戰乮暋悢慖戰壜乯偟偨丏夝愅偼丆庡帯堛偑擖堾偵帄偭偨偲敾抐偟偨NPI偺崁栚偺偆偪丆昿搙偺崅偄忋埵4偮偺崁栚偵偍偄偰丆偦偺崁栚偵傛傝擖堾偲側偭偨姵幰孮偲丆偦偆偱偼側偄姵幰孮偲偺丆摉奩NPI偺斾妑傪峴偭偨乮椺偊偽丆栂憐偵傛傝擖堾偵帄偭偨姵幰N柤偲丆栂憐偼擖堾偺尨場偱偼側偄姵幰M柤偲偺丆NPI偺栂憐偺愊偺斾妑傪峴偭偨乯丏
- 亂椣棟揑攝椂亃屄恖傪摿掕偣偢丆夝愅偱偼摻柤壔偵攝椂偟偨丏
- 亂寢壥亃慡巤愝偱176柤偑BPSD帯椕栚揑偱擖堾偟偨丏17柤偼恎懱幘姵偺帯椕偺偨傔偵揮堾丆傑偨偼巰朣偵傛傝拞巭丆偝傜偵19柤偼2010擭11寧30擔帪揰偱擖堾宲懕偟偰偍傝丆宱夁娤嶡拞偱偁傞偨傔崱夞偺夝愅偐傜偼彍奜偟偨丏夝愅偺懳徾偲側偭偨偺偼140柤偱偁偭偨丏
丂NPI偺崁栚偺偆偪丆庡帯堛偑丆姵幰偑擖堾偵帄偭偨偲敾抐偟偨崁栚偼丆嫽暠丆栂憐丆堎忢峴摦丆悋柊偺弴偵懡偔丆弎傋恖悢偼偦傟偧傟丆96恖丆62恖丆60恖丆58恖偱偁偭偨丏
丂栂憐偑擖堾偺尨場偵側偭偨姵幰62柤偺NPI栂憐偺愊偼7.7亇3.9偱丆尨場偵側偭偰偄側偄姵幰78柤偱偼3.4亇4.3偱偁偭偨丏擖堾偵帄傞掱搙傪柧傜偐偵偡傞偨傔丆姶搙偲摿堎搙偑嫟偵崅偔側傞傛偆愝掕偡傞偲丆NPI偺栂憐偺愊偺僇僢僩僆僼偼6乮姶搙0.69丆摿堎搙0.71乯偲側偭偨丏摨條偵丆嫽暠偑擖堾偺尨場偲側偭偨姵幰96柤偱偼7.7亇3.8丆尨場偵側偭偰偄側偄姵幰44柤偱偼5.0亇4.0偱丆僇僢僩僆僼偼8乮姶搙0.65丆摿堎搙0.66乯丆堎忢峴摦偑擖堾偺尨場偲側偭偨姵幰60柤偱偼8.0亇4.2丆尨場偵側偭偰偄側偄姵幰80柤偱偼5.4亇4.9偱丆僇僢僩僆僼偼8乮姶搙0.68丆摿堎搙0.6乯丆悋柊偑擖堾偺尨場偲側偭偨姵幰58柤偱偼8.2亇3.5丆尨場偵側偭偰偄側偄姵幰82柤偱偼5.0亇4.6偱丆僇僢僩僆僼偼6乮姶搙0.81丆摿堎搙0.54乯偲側偭偨丏
- 亂峫嶡亃姵幰傪擖堾偵帄傜偟傔傞BPSD偺偆偪昿搙偺崅偄徢忬偼丆嫽暠丆栂憐丆堎忢峴摦丆悋柊忈奞偱偁傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丏傑偨庡帯堛偑偦傟偧傟偺徢忬偵傛傝擖堾偑昁梫偲敾抐偡傞掱搙傕柧傜偐偲側偭偨丏崱屻丆擣抦徢姵幰悢偼憹壛偡傞偑丆BPSD傪帯椕偡傞偨傔偺昦彴悢偵偼尷傝偑偁傞丏崱夞偺挷嵏寢壥偑丆擖堾偺昁梫惈傗桪愭搙傪敾抐偡傞栚埨偵側傞偲峫偊傞丏傑偨丆昿搙偺崅偄徢忬偺偆偪丆悋柊忈奞偼帯椕岠壥偑摼傗偡偄徢忬偱偁傝丆擖堾姵幰悢傪尭彮偝偣傞偨傔偵偼丆傑偢奜棃恌椕偵偍偄偰悋柊忈奞偺帯椕傪廫暘偵峴偆昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞丏
丂杮尋媶偼丆岤惗楯摥壢妛尋媶旓曗彆嬥擣抦徢懳嶔憤崌尋媶帠嬈乽擣抦徢偺峴摦怱棟徢忬偵懳偡傞尨場幘姵暿偺帯椕儅僯儏傾儖偲楢実僋儕僯僇儖僷僗嶌惉偵娭偡傞尋媶乿偺堦娐偱峴傢傟偨丏
- P-B-4丂
- 寣塼摟愅姵幰偵偍偗傞擣抦婡擻掅壓偵娭偡傞墶抐揑尋媶
- 彫揷嬎丂尦乮峅慜戝妛戝妛堾恄宱惛恄堛妛島嵗乯
- 亂栚揑亃摟愅媄弍偺恑曕傗摟愅摫擖擭楊偺忋徃偵傛傞摟愅姵幰偺媫懍側崅楊壔偑巜揈偝傟偰偄傞丏摟愅姵幰偵偍偗傞擣抦婡擻掅壓偺曬崘偼嶶尒偝傟傞傕偺偺丆堦斒寬峃廧柉偲偺斾妑傪峴偭偨尋媶偼傎偲傫偳傒傜傟側偄偺偑尰忬偱偁傞丏杮尋媶偱偼丆摟愅姵幰偵偍偗傞擣抦婡擻掅壓偲偦傟偵娭傢傞梫場傪専摙偡傞傎偐丆堦斒寬峃廧柉偲偺斾妑偵傛傝摟愅姵幰偺擣抦婡擻掅壓偺儕僗僋偵偮偄偰昡壙偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丏
- 亂曽朄亃A導偵偁傞昦堾偱摟愅拞偺姵幰154柤偲2008擭偵娾栘寬峃憹恑僾儘僕僃僋僩傊嶲壛偟偨30嵨埲忋偺堦斒寬峃廧柉863柤乮抝惈317柤丆彈惈546柤乯傛傝尋媶嶲壛偺摨堄傪摼偰丆懳徾幰偲偟偨丏姵幰孮偺挷嵏偼2009擭9寧傛傝2010擭1寧傑偱偺婜娫偵幚巤偟偨丏
丂擣抦婡擻偺昡壙偵偼Mini乚Mental State Examination乮MMSE乯偺擔杮斉傪巊梡偟偨丏擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢丆摟愅擭悢偵娭偡傞忣曬偼丆帺婰幃傾儞働乕僩傛傝摼偨丏婛墲楌傗嵦寣偵傛傞惗壔妛僨乕僞偼恌椕榐傛傝庢摼偟偨丏側偍丆MMSE偵偮偄偰偼丆23揰埲壓傪擣抦婡擻掅壓偲偡傞僇僢僩僆僼抣傪嵦梡偟偨丏
丂姵幰孮偵偍偄偰MMSE摼揰偵塭嬁傪梌偊傞場巕偵偮偄偰丆擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢丆摟愅擭悢丆愒寣媴悢丆Alb丆Na丆K丆UA丆僋儗傾僠僯儞丆擜慺拏慺丆摟愅屻懱廳丆摟愅検乮Kt/V乯傪撈棫曄悢偲偟偰廳夞婣暘愅傪幚巤偟偨丏峏偵丆堦斒寬峃廧柉偲偺斾妑偱偼丆擭楊丆惈暿丆嫵堢擭悢傪嫟曄悢偲偟偨丆儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅傪峴偭偨丏側偍丆偄偢傟傕桳堄悈弨偼p亙0.05偵愝掕偟丆暯嬒抣亇昗弨曃嵎偱僨乕僞傪帵偟偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃杮尋媶偺幚巤偵愭棫偪丆峅慜戝妛戝妛堾堛妛尋媶壢椣棟埾堳夛偺彸擣傪摼偨丏
- 亂寢壥亃姵幰孮偼擭楊65.1亇13.3嵨偱丆嫵堢擭悢偼10.7亇2.5擭丆摟愅擭悢偼7.8亇6.4丆傑偨丆MMSE摼揰偼26.6亇3.9揰偱偁偭偨丏
丂姵幰孮偵偍偗傞廳夞婣暘愅偱丆MMSE摼揰偲擭楊乮兝亖亅0.205丆t亖亅2.088丆P亙0.05乯丆嫵堢擭悢乮兝亖亅0.289丆t亖3.554丆P亙0.01乯丆寣拞Na乮兝亖0.173丆t亖2.286丆p亙0.05乯丆擼寣娗幘姵偺婛墲乮兝亖亅0.225丆t亖亅3.069丆p亙0.01乯偲偺娫偵娭楢惈傪擣傔偨丏峏偵丆儘僕僗僥傿僢僋夞婣暘愅偵偰丆寬姵幰孮偑寬忢孮偵斾偟偰丆MMSE23揰埲壓傪庢傞僆僢僘斾偑2.28乮95亾 C.I.丟1.33亅3.94丆p亙0.01乯偱偁傞偙偲傕帵偝傟偨丏
- 亂峫嶡亃姵幰孮偵偍偄偰偼寣拞Na埲奜偺嵦寣崁栚偱MMSE偲偺娭楢惈傪擣傔側偐偭偨傕偺偺丆寬忢孮偲斾傋丆擣抦婡擻掅壓傪惗偠傞僆僢僘斾偼2攞埲忋偱偁偭偨丏擣抦婡擻掅壓傪惗偠傞丆僴僀儕僗僋廤抍偲偟偰摟愅姵幰偺恌椕傪峴偆昁梫惈偑偁傞偲峫偊傜傟偨丏
- P-B-5丂
- 憤崌昦堾惛恄壢昦搹偵偍偗傞崅楊擖堾姵幰偺嵼堾擔悢偵塭嬁傪媦傏偡梫場偺専摙乮偦偺2乯
- 栰杮丂廆岶乮墶昹巗棫戝妛晬懏巗柉憤崌堛椕僙儞僞乕惛恄堛椕僙儞僞乕丆墶昹巗棫戝妛惛恄堛妛嫵幒乯
- 亂栚揑亃憤崌昦堾惛恄壢昦彴偵偍偗傞崅楊擖堾姵幰偼丆恎懱崌暪徢傗娐嫬挷惍側偳庬乆偺梫場偵傛偭偰嵼堾擔悢偑挿婜壔偡傞偙偲偑曬崘偝傟偰偄傞丏崅楊擖堾姵幰偺嵼堾擔悢偵塭嬁傪媦傏偡梫場傪柧傜偐偵偡傞偨傔丆摉僙儞僞乕偵擖堾偟偨60嵨埲忋偺姵幰恌椕榐傪慜曽帇揑偵挷嵏偟偨丏2擭慜偺曬崘偐傜徢椺偺偝傜側傞廤愊偑摼傜傟偨偨傔丆偦偺寢壥傪壛偊偰曬崘偡傞丏
- 亂懳徾偲曽朄亃摉僙儞僞乕偼惛恄壢媬媫婎姴昦堾偱偁傝丆昦搹偼50彴乮奐曻28彴丆暵嵔22彴丆偆偪妘棧幒7彴乯偺惛恄壢昦彴偱峔惉偝傟偰偄傞丏暯惉20擭12寧偐傜暯惉23擭1寧偺娫偵摉僙儞僞乕偵擖堾偟偨60嵨埲忋偺姵幰30徢椺偵偮偄偰丆嵼堾擔悢丆惛恄堛妛揑恌抐乮DSM乚嘩乯丆摨嫃幰偺桳柍丆擖堾宍懺丆擖堾慜偺廧娐嫬丆恎懱崌暪徢偺桳柍丆擖堾拞偺桝塼丒宱娗塰梴丒擜摴僇僥乕僥儖偺巤峴偺桳柍丆妘棧丒恎懱峉懇偺巤峴偺桳柍丆壠懓偺僒億乕僩懺惃偺傎偐丆恌抐偵傛偭偰擖堾帪偲戅堾帪偺僴儈儖僩儞偆偮昦昡壙広搙乮HAM乚D乯丆Mini乚Mental State Examination乮MMSE乯丆Brief Psychiatric Rating Scale乮BPRS乯丆Barthel index傪挷傋丆慄宍夞婣暘愅丆僂傿儖僐僋僜儞専掕側偳偺摑寁妛揑庤朄偵傛傝嵼堾擔悢偵塭嬁偡傞場巕偺専摙傪峴偭偨丏
- 亂椣棟揑攝椂亃弶恌帪丆椪彴尋媶偵娭偡傞曪妵摨堄彂傪偲偭偰偍傝丆偄偢傟偺昡壙崁栚偵偮偄偰傕姵幰偺帯椕偵嵺偟偰怤廝揑偵摥偔偙偲偼側偔丆寢壥偺夝愅偵偮偄偰偼摻柤惈偑曐偨傟傞傛偆廫暘側攝椂傪偍偙側偭偨丏
- 亂寢壥亃暯嬒嵼堾擔悢偼31.5擔偱偁傝丆嵟抁擔悢偼7擔丆嵟挿擔悢偼96擔偱偁偭偨丏恎懱崌暪徢傪桳偡傞徢椺偍傛傃擣抦婡擻掅壓徢椺偱嵼堾擔悢偑挿偔側傞孹岦偑傒傜傟偨丏傑偨丆惛恄壢揑恌抐暿偺嵼堾擔悢偱偼丆擣抦徢徢椺偑嵼堾擔悢偑挿偄孹岦偑擣傔傜傟偨丏
- 亂峫嶡亃憤崌昦堾惛恄壢昦搹偵偍偄偰崅楊擖堾姵幰偺嵼堾擔悢偵塭嬁傪媦傏偡梫場偺専摙傪偍偙側偭偨丏崱擔丆嵼堾擔悢偺抁弅偼惛恄壢恌椕偵偍偄偰傕旔偗偰捠傟側偄壽戣偺堦偮偱偁傞丏帯椕偦偺傕偺偵梫偡傞帪娫埲奜偵傕丆働乕僗儚乕僋偵梫偡傞帪娫偑挿婜偵傢偨傞働乕僗偑懡偔擣傔傜傟偰偄傞丏擖堾帪偵奺徢椺偵偮偄偰傾僙僗儊儞僩傪峴偄丆傛傝憗婜偵擖堾帯椕偐傜嵼戭帯椕傊偺堏峴傪偡偡傔傞偙偲偑媮傔傜傟傞丏摉擔偼偝傜偵徢椺悢傪憹傗偟丆嵼堾擔悢偵塭嬁傪媦傏偡梫場偵偮偄偰柧傜偐偵偡傞偲偲傕偵丆擖堾擔悢抁弅偺曽嶔偲栤戣揰偵偮偄偰曬崘偟偨偄丏
-
- 丂
- 丂
- 丂